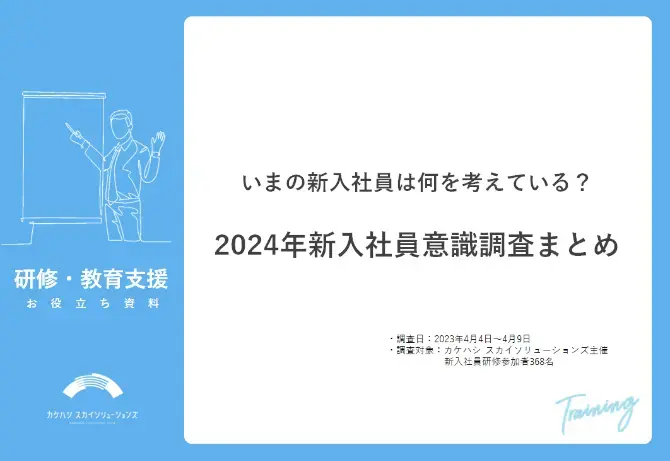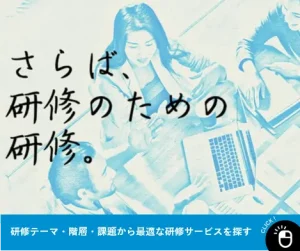時短ハラスメントとは、社員に対して労働時間の短縮を強制するハラスメントのこと。
政府が主導する「働き方改革」の影響を受け、近年注目を集めているハラスメントです。
今回は、時短ハラスメントの概要やデメリットのほか、企業ができる対策について詳しく解説します。
自社で時短ハラスメントを起こさないために、本記事をお役立てください。
目次 [非表示]
時短ハラスメントとは?
 時短ハラスメントとは、上司が部下に対し、残業の削減や定時での退社を強要する行為のことです。
時短ハラスメントとは、上司が部下に対し、残業の削減や定時での退社を強要する行為のことです。
略して、ジタハラとも呼ばれます。
時短ハラスメントが起きている背景には、政府が進めている「働き方改革」の影響があります。
働き方改革への取り組みとして、企業が長時間労働の是正や残業削減の取り組みをおこなっていることから、時短ハラスメントが発生しやすい状況になっています。
社員が実際に抱えている業務量やそれに適した労働時間を会社側が把握せず、一方的に労働時間の削減を強制することは、時短ハラスメントに該当すると言えます。
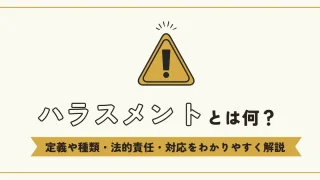
時短ハラスメントの発生状況
企業における時短ハラスメントの実態を調査するべく2017年11月、株式会社 高橋書店は全国のビジネスパーソン730名を対象として、「働き方改革に関するアンケート調査」を実施しました。
その結果、『あなたの会社で「働き方改革」(長時間労働の改善)に関する取り組みが導入されたことにより、困っていることはありますか?』という設問に対し、約4割の人が、「働ける時間が短くなったのに、業務量が以前のままのため、仕事が終わらない」と回答しています。
また、上位回答には、「仕事が終わっていなくても、定時で帰らなければならない」「長時間労働を改善するための、具体的な現場の対策・体制がまだ整っていないため、スタッフ間で混乱が起きたことがある」との声もありました。
このように、働き方改革(長時間労働の改善)に取り組む企業に勤めているビジネスパーソンは、時短ハラスメントにつながる悩みを抱えているという現状が明らかになっています。
(参考:株式会社 高橋書店『「働き方改革」に取り組む企業に勤めるビジネスパーソンの約8割が業務効率化・生産性向上のために「紙の手帳」を活用!』)
時短ハラスメントが発生する原因とは?
 前述したアンケート調査からもわかる通り、時短ハラスメントが発生する原因には、働き方改革を進めた結果、「業務量は減っていないにもかかわらず、労働時間だけが減っている」という理由が挙げられます。
前述したアンケート調査からもわかる通り、時短ハラスメントが発生する原因には、働き方改革を進めた結果、「業務量は減っていないにもかかわらず、労働時間だけが減っている」という理由が挙げられます。
企業が働き方改革を推進するために社員の残業時間を減らすこと自体には、何も問題はありません。
しかし、上司が部下に対して適正なマネジメントをせず、無理なスケジュールを組んだり業務を押し付けたりするなど、残業時間を減らすための対策が何もなされないことが問題となるのです。
業務量自体は減っていないため、業務時間内で完了できなかった業務を社員は自宅に持ち帰り、サービス残業をせざるを得なくなる場合もあります。
働き方改革が目指すものは、単に労働時間を短縮することではありません。
労働時間を短縮しても、同じ成果を上げられるようにするため、業務効率を上げることにあります。
残業時間の削減や定時退社を促すだけでは、時短ハラスメントが発生しやすくなると言えます。
時短ハラスメントがもたらすデメリット
 時短ハラスメントが起こると、企業には以下のようなデメリットが生じます。
時短ハラスメントが起こると、企業には以下のようなデメリットが生じます。
- 離職者や休職者が増える
- 生産性や業務品質が低下する
- 企業のブランドイメージが低下する
デメリットについて具体的に見ていきましょう。
離職者や休職者が増える
時短ハラスメントは、離職者や休職者を増やす恐れがあります。
時短ハラスメントは社員にストレスや不安を与えます。
仕事がまわらない状況にプレッシャーを感じ精神的に追い詰められることにより、心身の健康を害した結果、離職せざるを得ないケースもあります。
また、離職者が増えることで他の社員へ業務のしわ寄せがいくこととなります。
残った社員の業務負担が増加するため、さらに離職者が増えるという負のスパイラルに陥る危険性もあります。
生産性や業務品質が低下する
業務量は減っていないのに労働時間を短縮すれば、社員はいい加減な仕事をするようになります。
納期がある業務は、その納期に間に合わせるように粗雑に業務をおこなうこととなり、業務品質が低下します。
業務上のミスも増えることで修正作業などが発生し、生産性の低下にもつながります。
就業時間内に終わらない仕事はサービス残業で対応するケースも発生するため、社員は労働に対する正当な対価が得られないことにより仕事へのモチベーションが低下し、積極的に仕事に取り組めなくなります。
また、部下が就業時間内に完了できなかった業務をその直属の上司である中間管理職がおこなう場合もあります。
部下の仕事を請け負うことで、中間管理職の負担が増える恐れもあるでしょう。
企業のブランドイメージが低下する
企業のブランドイメージを低下させることも時短ハラスメントのデメリットです。
近年は、XなどのSNSを通じ、企業の評判は簡単に広まってしまいます。
サービス残業を強要しているといった悪評は、企業のブランドイメージを低下させるだけではなく、企業の売り上げや人材獲得にも影響を与えます。
また、時短ハラスメントが訴訟につながるケースもあります。
企業に対する社会的責任が求められる昨今、時短ハラスメントが起こることは、企業に大きなダメージを与えると言えるでしょう。
時短ハラスメントの実例

企業では実際、どのような時短ハラスメントが起こっているのでしょうか。
ここからは、時短ハラスメントの実例をご紹介します。
サービス残業をしている教育現場の実例
県高校教職員組合が2019年におこなったアンケートによると、県立高など県立学校の教職員の2人に1人が、タイムカードの打刻後に仕事をしたり、打刻しないまま休日出勤したりしている実態が明らかになりました。
上司から定時で退社するよう言われる一方、仕事量が減っていないため、打刻時間を調整したり、休日に自宅で仕事をおこなったりしているようです。
働き方改革を進める中で、すべての県立高校ではタイムカードが導入されましたが、実際には「闇営業」が横行する形となっていることが浮き彫りとなりました。
(参考:NPO法人 働き方ASU‐NET『「早く帰れと言われても仕事が…」 教職員の半数が“闇残業” 県高校組合アンケート』)
過労自殺し裁判にまで発展した実例
時短ハラスメントが原因で過労自殺し、裁判に発展した実例もあります。
自動車販売店の管理者であるAさんは、上長から「仕事は早く終わらせろ、でも社員は早く帰せ」と言われていました。
部下の分まで仕事を抱え、家に持ち帰って仕事をしており、精神的、肉体的に多大なストレスを抱えて失踪。
その後、会社から懲戒解雇が通知され裁判にまで発展し、身体を壊して自殺にまで至ってしまったのです。
このように、時短ハラスメントが原因で、自殺に追い込まれるようなケースもあります。
(参考:NPO法人 働き方ASU‐NET『自動車販売店長自殺 「時短ハラスメント」拡大の恐れ』)
時短ハラスメントを起こさないための方法
 時短ハラスメントにより起こり得るさまざまな問題を防ぐために、企業としてどのようなことができるのでしょうか。
時短ハラスメントにより起こり得るさまざまな問題を防ぐために、企業としてどのようなことができるのでしょうか。
ここからは、時短ハラスメントを防ぐためにできる具体的な方法についてご紹介します。
業務量の把握と見直し
時短ハラスメントを起こさないためには、業務量を把握し、見直すことが重要です。
業務量が変わらないまま労働時間の削減だけを要求すると、負担が増えるばかりで、社員は疲弊してしまいます。
まずは、業務の作業工程を洗い出し、無駄な作業がないかを確認しましょう。
上司など管理職が業務量と労働時間のバランスを考えながら時間管理をおこなうことも重要ですが、社員一人ひとりが自身の抱えている業務を見直すことも大切です。
その結果、誰か一人に業務負担が偏っている場合は、ほかの人にお願いするなど業務分担を検討しましょう。
現状の業務量が適正か、誰かに負担が偏っていないかを把握するために、定期的にヒアリングをおこなうことも効果的です。
現場の意見を吸い上げるための環境を整備するとよいでしょう。
上司と部下のコミュニケーションの円滑化
先に述べたように、適正な労働時間を把握するためには、管理する上司がその現状をしっかり把握する必要があります。
上司からのヒアリングがおこなわれた場合も、上司とのコミュニケーションがうまくとれていない状態だと部下は正確に状況を伝えることができないため、意味のないものになってしまいます。
信頼関係を築くための取り組みとして、上司へのマネジメントやハラスメントに関する研修に加え、1on1の実施なども有効です。
上司と部下の間でコミュニケーションが円滑におこなわれていれば、業務量の見直しなども順調に進み、時短ハラスメントを防ぐことができます。
時短ハラスメントを受けている側は、ハラスメントの状況を報告することで不当な扱いを受けるなど不利益を被るのではないかといった、不安を抱える可能性もあります。
安心して声を上げられる仕組みとして、相談窓口を設置することも大切です。
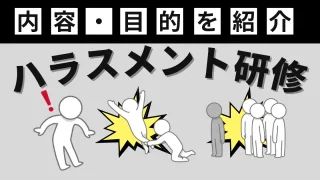
業務の改善
業務の把握や見直しをおこなっても労働時間の短縮が見込めないケースもあります。
そういったケースでは、業務の効率化を検討することも、時短ハラスメントを起こさないための方法です。
例えば、業務を効率化できるITツールなどを導入するのもよいでしょう。
ツールには、以下のように、目的に応じたさまざまなタイプがあります。
- 業務自動化ツール(RPA):データ集計などの定型業務を自動化できる
- タスク管理ツール:チームの進捗状況やタスクを可視化できる
- コミュニケーションツール:社内外での情報共有や相談を簡単におこなえる
- Web会議ツール:時間や場所を選ばず会議を開催できる
必要な機能や導入目的を見極め、自社にとって適切なツールを活用するとよいでしょう。
まとめ
 時短ハラスメントが起こると、離職者や休職者が増えるほか、生産性や業務品質が低下するなどのデメリットが生じます。
時短ハラスメントが起こると、離職者や休職者が増えるほか、生産性や業務品質が低下するなどのデメリットが生じます。
そのため企業は時短ハラスメントを起こさないよう業務量の把握や見直し、改善のほか、社内のコミュニケーションを円滑にするなどの対策をおこなうとよいでしょう。
採用・育成・定着を支援し、さまざまなソリューションをワンストップで提供するカケハシ スカイソリューションズでは、管理職や一般社員を対象としたハラスメント研修をご用意しています。
カケハシ スカイソリューションズのハラスメント研修では、ハラスメントが起きる根本的な原因を理解し、ハラスメントを根絶する組織を作るための考え方と手法を学べます。
ご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。
おすすめの管理職対象研修
開催中の無料セミナー
NG行動・ケーススタディばかり教えていませんか?
多くのハラスメント研修の落とし穴を解説。
管理職に求められるハラスメント教育のポイントセミナー
開催日時:
2025年4月23日(水)13:00-14:00
2025年5月20日(火)13:00-14:00
貴社はどんなeラーニングが向いている?
30分でわかる!失敗しないeラーニングの選び方セミナー
開催日時:
2025年4月24日(木)13:00-13:30
2025年5月23日(金)13:00-13:30
多様なキャリアの社員を活躍させ、
価値を最大化できる管理職を育てる
管理職育成・スキル強化のための相談会
開催日時:ご希望の日時で承ります
※ご予約後、担当より日程調整のご連絡を差し上げます
おすすめのお役立ち資料
すべて無料でダウンロードできます。
フォームに必要事項入力後、回答完了画面にてダウンロード可能です。
気になる資料があれば、ぜひご一読ください!
社員研修の他、各分野のお役立ちコラムを公開中
社員研修の知恵袋の他、新卒採用の知恵袋、中途採用の知恵袋、離職防止の知恵袋を運営しています。ぜひ合わせてご覧ください。
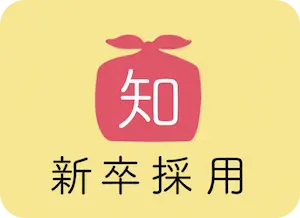 |
 |
 |
 |
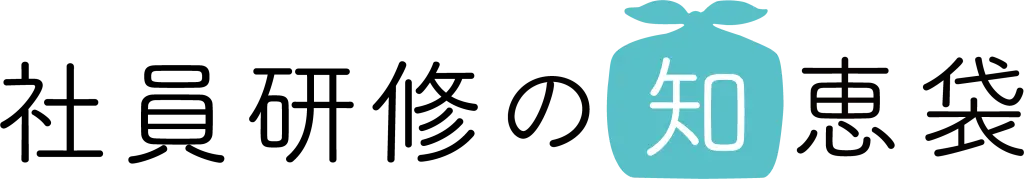
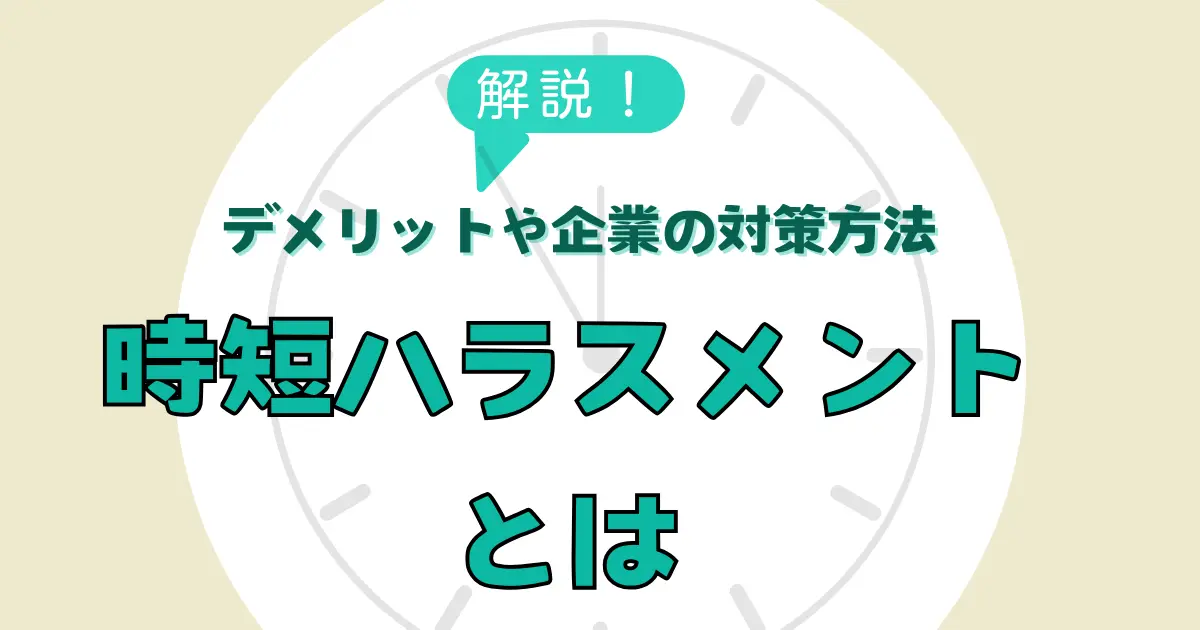
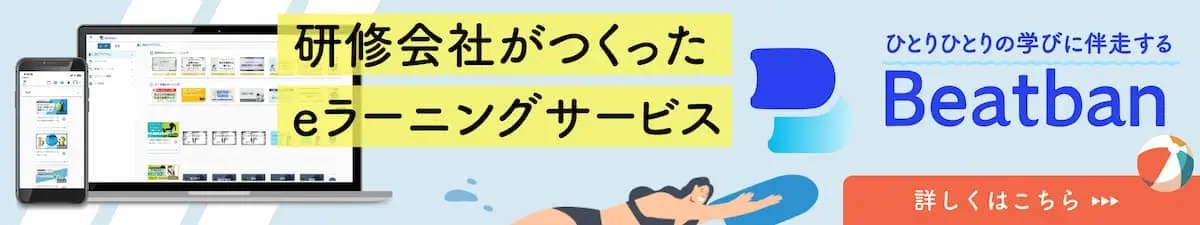

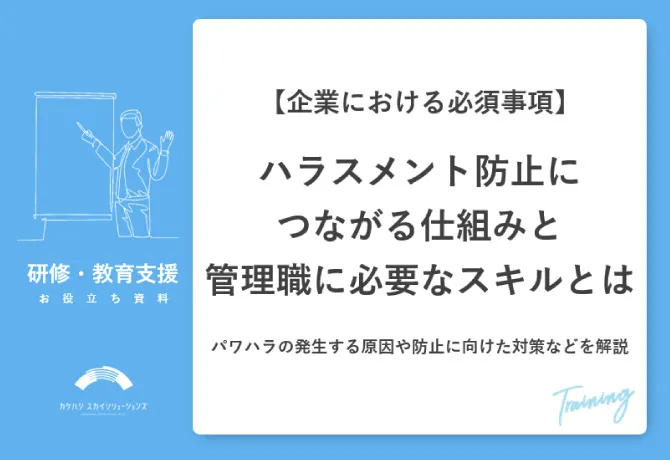
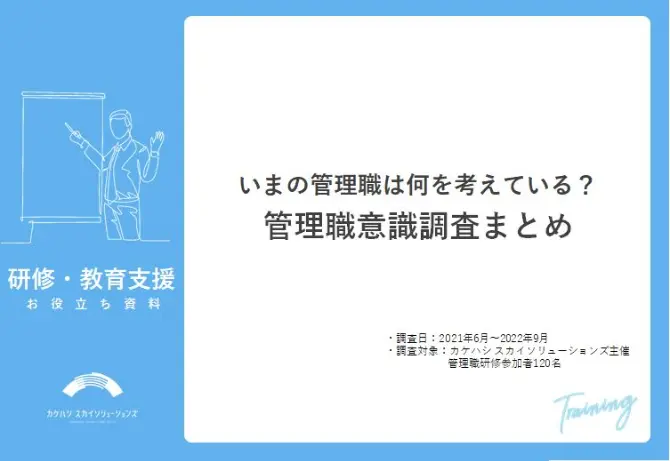
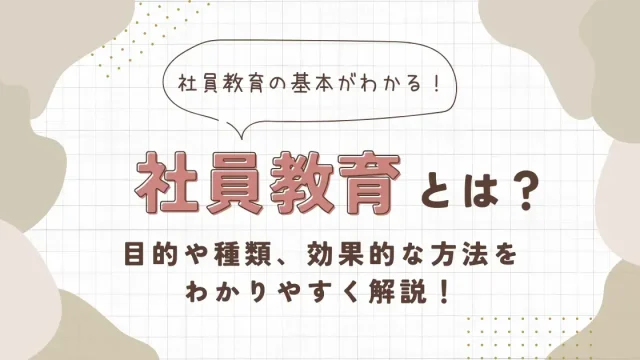

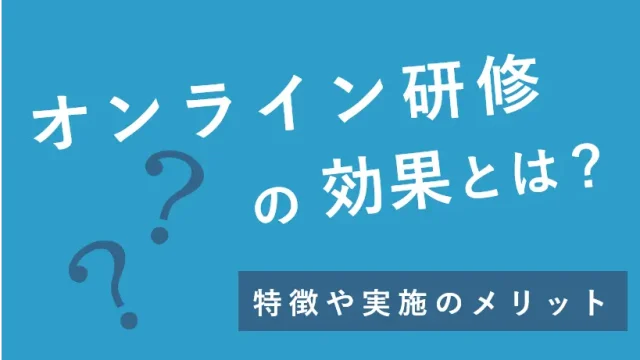
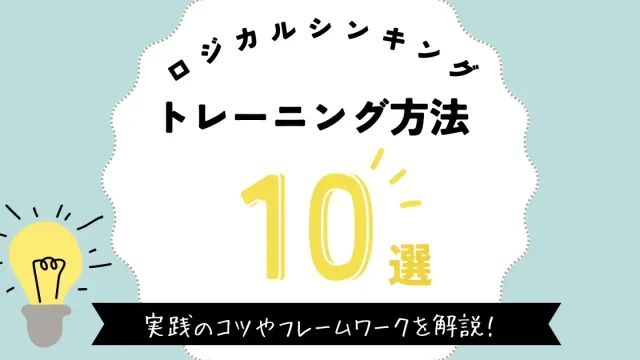
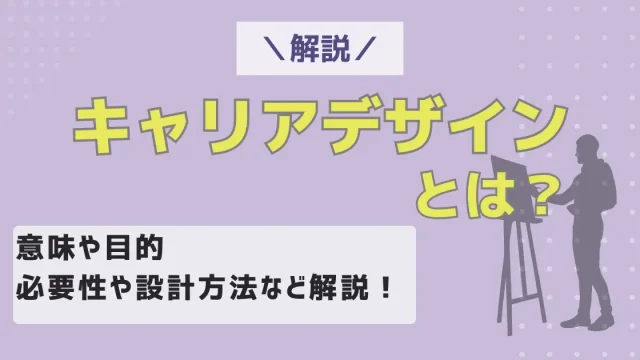
 組織の力を最大化する育成のポイントガイドブック
組織の力を最大化する育成のポイントガイドブック 
 離職防止につなげるオンボーディング活用ガイドブック
離職防止につなげるオンボーディング活用ガイドブック 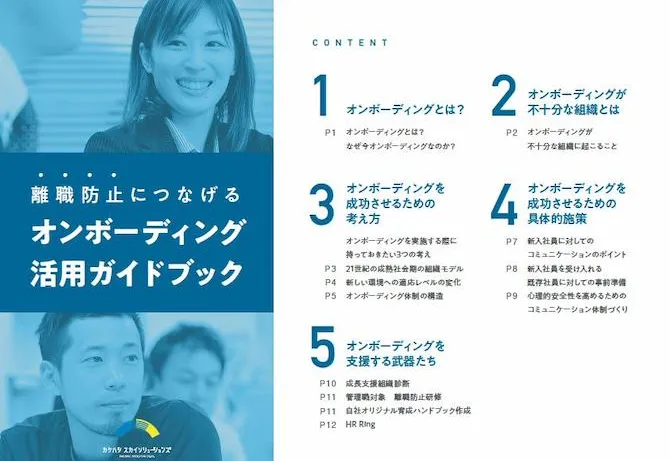
 2024年新入社員意識調査まとめ
2024年新入社員意識調査まとめ