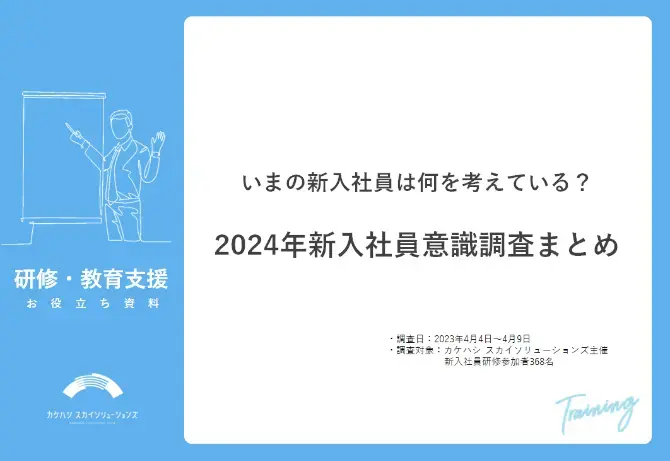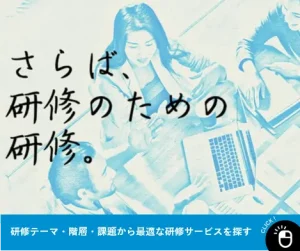パソコンなどの電子機器とインターネットを活用する教育手法の「eラーニング」。
学習履歴により進捗率や達成度合いを把握でき、体系的な教育を提供できると考えられています。
オンラインで実施できる社員教育として多くの企業で導入されていますが、実際に取り組んでいる社員の中には「意味がない」と不満を感じている人も少なくないようです。
今回の記事では、「eラーニングは意味がない」と言われてしまう原因や理由、管理者が抱える課題についてご紹介します。
目次 [非表示]
eラーニングに対して社員が「意味がない」と感じてしまう7つの原因
 eラーニングは、「いつでもどこでも学習できる」「何度も復習できる」などのメリットがありますが、実際に取り組む社員の中には「意味がない」と不満を感じる人もいるようです。
eラーニングは、「いつでもどこでも学習できる」「何度も復習できる」などのメリットがありますが、実際に取り組む社員の中には「意味がない」と不満を感じる人もいるようです。
ここではeラーニングに対して社員が「意味がない」と感じる原因を7つご紹介します。
- 特定のOSやデバイスにしか対応していない
- 長時間のコンテンツで受講時間が長くなる
- 労働時間外に受講するケースがある
- 実務につながるという実感が得られない
- 学習管理がおざなりになっている
- 質疑応答やディスカッションができない
- 受講意欲やモチベーションが続かない
特定のOSやデバイスにしか対応していない
導入するeラーニングが特定のOSやデバイスにしか対応していないと、社員の不満につながる場合があります。
例えば、「専用のソフトが必要」「社内システムからしかアクセスできない」など、eラーニングを開始するまでに手間がかかると、実施自体が面倒に感じてしまうためです。
また、若手社員がスマートフォンでの学習を希望するように、各社員が利用しやすいデバイスに対応しているかどうかも重要なポイントです。
デバイスが限られると使い勝手が悪く、普及しない原因にもなります。
長時間のコンテンツで受講時間が長くなる
eラーニングの想定再生時間は30~60分が一般的ですが、社員に前提知識がないと理解するのに時間がかかり、受講時間が長くなってしまうことがあります。
忙しい業務の合間に受講する社員もいるため、コンテンツの時間が長くなると「自分の時間が奪われている」と感じて不満につながるようです。
また、長時間のコンテンツは途中で飽きて、読み飛ばしや早送りしてしまう原因にもなります。
労働時間外に受講するケースがある
eラーニングの受講時間は労働時間としてカウントするのが一般的ですが、そうではない企業が多いのが現状のようです。
労働時間外にeラーニングを受講することになっても、学習時間に対して残業代がつかないことにより、社員の不満を招いているケースもあります。
eラーニングの受講時間が労働時間に該当するか否か、ルールが明確化されていないことが不満を生む原因になっていると言えます。
実務につながるという実感が得られない
eラーニングで学ぶコンテンツを実務で活かすイメージが湧かない場合にも、「意味がない」と感じてしまいます。
アウトプットできる機会がない、応用が難しいといったケースも少なくありません。
社員のモチベーションを下げないためにも、ディスカッションやケーススタディなどを取り入れた、より実践的な学習内容にすることが求められます。
eラーニングの内容が、実務につながる知識やスキルを学べるプログラムになっているか確認しておきましょう。
また、受講した社員にアンケートを実施したり、フィードバックを受けたりと、企業側が研修内容の見直しとアップデートをすることも大切です。
学習管理がおざなりになっている
eラーニングにおいて社員の学習管理がおざなりになってしまうのも、「意味がない」と思われる理由の一つです。
社員一人ひとりの学習管理を怠ってしまうと、eラーニングの効果が十分に得られません。
また、研修の進捗が遅れる、知識が偏る、学習コンテンツが適切に選定されないといった問題が生じる可能性もあります。
eラーニングは導入して終わりではありません。
導入後も適切な管理・運営をおこなって、社員から「意味がない」と思われないものにしましょう。
質疑応答やディスカッションができない
eラーニングは自己学習のため、学習中に不明点や疑問があってもその場で解決できない点も不満が生じる理由になります。
集合研修は社員間の交流機会としても役立つのに対し、eラーニングではそのような副次効果が得られません。
eラーニングだけで完結できる教育なのかを検討し、場合によっては集合研修と組み合わせるなどの工夫が求められます。
受講意欲やモチベーションが続かない
eラーニングの設計は自由度が高いため、受講者の受講意欲やモチベーションのコントロールが難しいことも理由に挙げられます。
同じ場所に集まっておこなう集合研修には強制力がありますが、eラーニングは個人単位で受講するため、「忙しくて忘れてしまった」「やる気がでない」などの理由でおざなりになってしまうことも「意味がない」と思われる原因として考えられます。
eラーニングが「意味ない」と感じられないようにする解決法
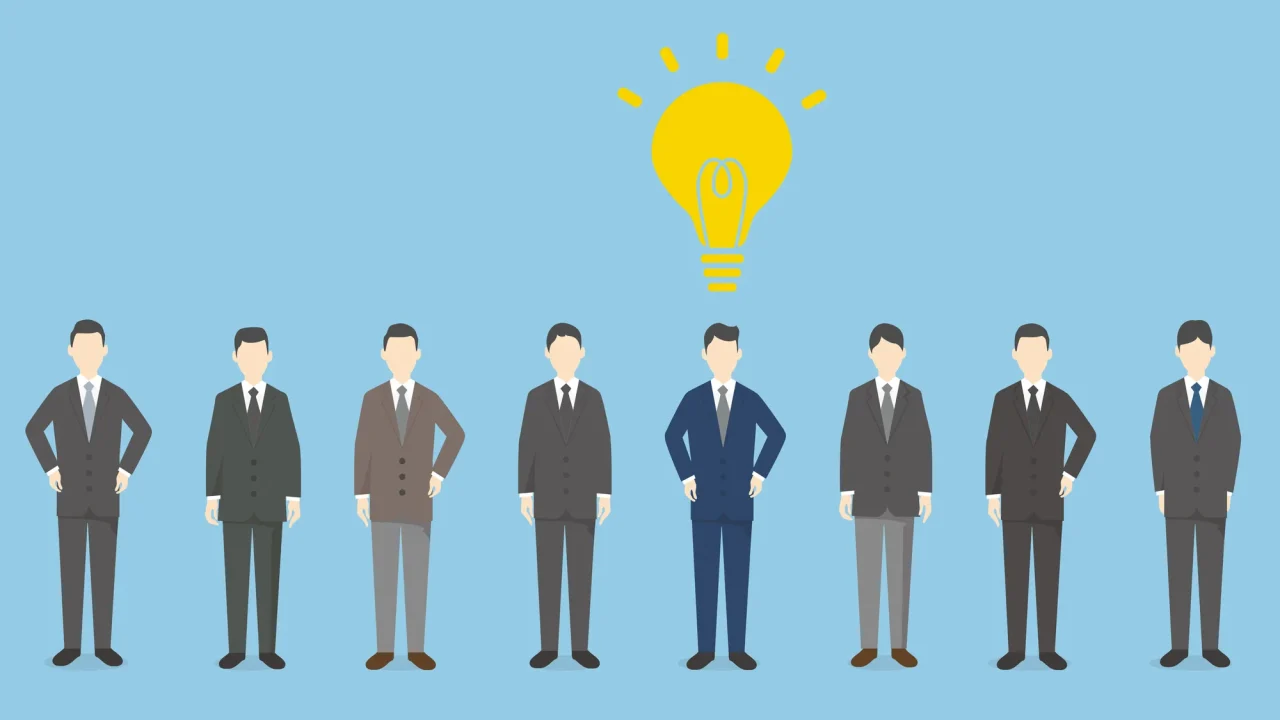 では、eラーニングを意味のあるものにするためには、どうすればよいのでしょうか。
では、eラーニングを意味のあるものにするためには、どうすればよいのでしょうか。
ここでは解決方法について具体的に解説していきます。
- UI・UXに優れたシステムを利用する
- ケーススタディなどを取り入れる
- eラーニングの取り組みを評価に組み込む
- 会社側である程度の学習管理をする
- 理解度をチェックできるコンテンツを導入する
UI・UXに優れたシステムを利用する
UI・UXに優れたeラーニングシステムを利用することで、使いやすい学習環境が実現できeラーニングの有用性が高まります。
システムが使いにくいと、学習効率が低下するだけでなく、学習する社員のモチベーション低下も招く恐れがあります。
UI・UXに優れたシステムを導入し直感的に操作できる学習環境にすることで、学習効率の向上が期待できます。
初めてeラーニングを使う社員に対しては、操作方法の説明会をおこなうなどサポート体制の整備も大切です。
ケーススタディなどを取り入れる
eラーニングのカリキュラムにケーススタディなどを取り入れて、コンテンツを充実させることも肝要です。
eラーニングで学んだ内容を実務で活かせないと、「意味がない」と感じてしまいがちです。
実務に直結するケーススタディや具体的な事例を用いた問題など、現場で役立つ実践的なスキルや知識を学べるコンテンツにしましょう。
また、インプットした内容を実践で活用するために、演習問題やシミュレーションをおこなうのもおすすめです。
学習後にアウトプットできる場を設けることで、学習効果の向上が見込めます。
eラーニングの取り組みを評価に組み込む
eラーニングでの成果を人事評価に組み込むのも、社員のモチベーションを上げる効果的な方法です。
時間をかけてeラーニングに取り組んでも、評価されなければ「意味がない」と捉えられてしまう可能性があります。
指定したコースを修了しスキルを身につけた社員に対して報酬や評価を与えるなど、学習意欲の向上を図りましょう。
また、eラーニングにおける学習態度や学習の記録、成果をデータ化できる学習管理システム「LMS」を活用して、評価に反映するのもおすすめです。
会社側である程度の学習管理をする
カリキュラムの選定や学習進捗の管理など、社員の学習管理を会社側でおこなうのも効果を上げる一つの方法です。
学習管理に特化した学習管理システム「LMS」を用いることで、社員一人ひとりの学習管理を一元化できます。
社員に適したカリキュラムを選定したり、進捗に遅延が発生している講座があれば学習を促すメールを送ったりと、学習のフォローが容易におこなえます。
テスト結果や学習履歴などがデータとして可視化されるため、社員の理解度や進捗が一目で把握できます。
理解度をチェックできるコンテンツを導入する
カリキュラムや講座ごとに、学習の理解度をチェックできるコンテンツを導入するとよいでしょう。
復習も兼ねてミニテストやクイズを実施し、社員が学習した内容をしっかりと理解できているかどうかを確認します。
重要なポイントを見逃していないか確認ができるため、学習効果の向上が期待できます。
eラーニングの効果を上げる方法
 eラーニングをより効果的なものにするためには、以下のような研修や制度と併用するのがおすすめです。
eラーニングをより効果的なものにするためには、以下のような研修や制度と併用するのがおすすめです。
- 対面の研修(ブレンディッドラーニング)
- OJT研修
- メンター制度
対面の研修と併用する(ブレンディッドラーニング)
対面式の研修を併用することで、eラーニングの効果を高められます。
この学習方法は、ブレンディッドラーニングとも呼ばれており、オンライン学習とオフライン学習の利点を活かした、高い学習効果が期待できます。
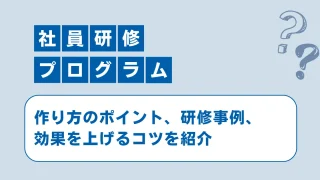
OJT研修と併用する
現場で実際の業務をおこないながら教育する「OJT(On The Job Training)」と併用します。
OJTを通じてeラーニングで学んだ知識をアウトプットすることで、学習内容の定着を促す効果があります。
また、OJTトレーナーを対象にeラーニングを実施すれば、属人化による教育内容や習得レベルのばらつき防止にもなります。

メンター制度と併用する
eラーニングの学習支援として、メンター制度を取り入れることもおすすめです。
メンター制度とは、後輩社員(メンティ) に対し、豊富な知識や職業経験のある社内の先輩社員(メンター)が個別におこなう支援活動のことです。
先輩社員が後輩社員に対し、悩みや課題を解決するためのサポートを実施します。
eラーニングにおける悩みや困りごとについて気軽に相談できる環境を作ることで、社員のモチベーションを維持・向上させましょう。
ここまで紹介したように、eラーニングの効果を上げるためには、eラーニングをどのように活用していくかが重要です。
カケハシ スカイソリューションズでは社員の学びが最大化するeラーニングの活用方法などもご提案していますので、少しでもご興味をお持ちいただけましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
また、カケハシ スカイソリューションズでは一人ひとりの学びに伴走するeラーニングサービス「Beatban」を提供しています。
従来のeラーニングにおける課題や不満を解決できる様々なサポートが完備されたeラーニングサービスです。詳細は以下よりご確認ください。
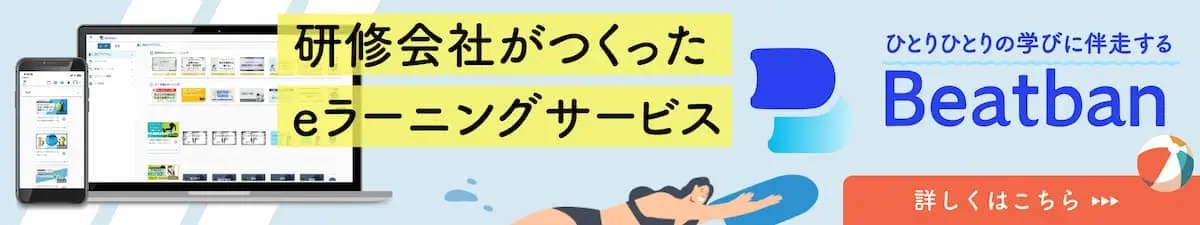
eラーニングの管理者が実際に抱える課題を聞いてみた
 eラーニングを受講する社員から「意味がない」との声が上がり、「eラーニングは効果が得られない」と感じている管理者もいるのではないでしょうか。
eラーニングを受講する社員から「意味がない」との声が上がり、「eラーニングは効果が得られない」と感じている管理者もいるのではないでしょうか。
eラーニングの管理者はどのような課題を抱えているのか、また、eラーニングで効果を得られていない企業が取り組みたい対策について、研修講師としての登壇実績が多数ある、カケハシ スカイソリューションズの教育研修事業部マネージャーにお話を伺いました。
教育研修事業部マネジャー
「eラーニングは効果が得られない」と感じてしまう一番の原因は?
eラーニングにも、よいところと悪いところがあります。それらを踏まえて、うまく活用できていないことで、効果を実感できないのではないでしょうか。
活用できていない原因の一つとして、導入時に「インストラクショナルデザイン」を検討できていないことが挙げられます。
インストラクショナルデザインとは、それぞれの環境において最適な教育効果を上げる「教育設計」のことで、研修の「狙い」「効果」「達成目標」を設定します。
eラーニングでの学習だけにとどめていては、実務に落とし込むことは難しいでしょう。
eラーニングの効果を高めるためには、インストラクショナルデザインをおこなった上で、「アウトプット学習」や「メンター制度」を組み合わせるなどの工夫が必要ですね。
eラーニングの管理者に求められることとは?
そもそもeラーニングの学習効果を期待しすぎている管理者が多いように感じています。
研修だけでは人は育ちません。
それを念頭に置いて、eラーニングで得た知識をいかに実務に落とし込めるかが管理者の課題になります。
実際に「できる」ことを目指すのが社会人の学びであるため、eラーニングで学んだ内容を社員がやりたいと思えるように、学びのプロセスを作って現場に送り出すことが大切ですね。
eラーニングで効果を得られていない企業が取り組みたい対策とは?
eラーニングの学習だけでは足りないところが発生します。
一方、eラーニングを活用することで効果的に学べることもあります。
例えば、リーダーシップ研修では経営知識として財務について学びます。
座学で学べる内容を、受講者全員で集まって学ぶ必要はありません。
受講期限を決めてそれぞれが知識を得た上で、より実務に近い対面型の研修ができれば研修効果も高まります。
また、基本的に働きながら学ぶことが前提なので、すき間時間に学べる「マイクロラーニング」などのコンテンツも有効です。
まとめ
 オンラインで実施できる社員教育として普及している「eラーニング」ですが、効果的に運営できていないことで、「意味がない」と感じる社員も多いようです。
オンラインで実施できる社員教育として普及している「eラーニング」ですが、効果的に運営できていないことで、「意味がない」と感じる社員も多いようです。
今回の記事で紹介した、社員が不満に感じる理由や活用されにくい原因にあるように、eラーニングだけでは学びを実務に活かしきれないと言えます。
実務で「できる」ようになるために、アウトプット学習やメンター制度を組み合わせる、あるいは短時間で効率よく学べるマイクロラーニングを導入することなどを検討してみてはいかがでしょうか。
おすすめの管理職対象研修
開催中の無料セミナー
NG行動・ケーススタディばかり教えていませんか?
多くのハラスメント研修の落とし穴を解説。
管理職に求められるハラスメント教育のポイントセミナー
開催日時:
2025年4月23日(水)13:00-14:00
貴社はどんなeラーニングが向いている?
30分でわかる!失敗しないeラーニングの選び方セミナー
開催日時:
2025年4月24日(木)13:00-13:30
多様なキャリアの社員を活躍させ、
価値を最大化できる管理職を育てる
管理職育成・スキル強化のための相談会
開催日時:ご希望の日時で承ります
※ご予約後、担当より日程調整のご連絡を差し上げます
おすすめのお役立ち資料
すべて無料でダウンロードできます。
フォームに必要事項入力後、回答完了画面にてダウンロード可能です。
気になる資料があれば、ぜひご一読ください!
社員研修の他、各分野のお役立ちコラムを公開中
社員研修の知恵袋の他、新卒採用の知恵袋、中途採用の知恵袋、離職防止の知恵袋を運営しています。ぜひ合わせてご覧ください。
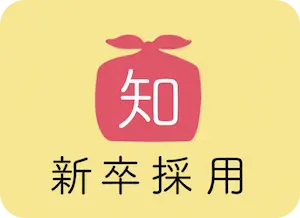 |
 |
 |
 |
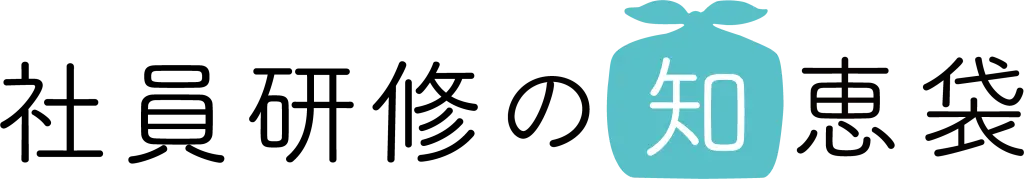
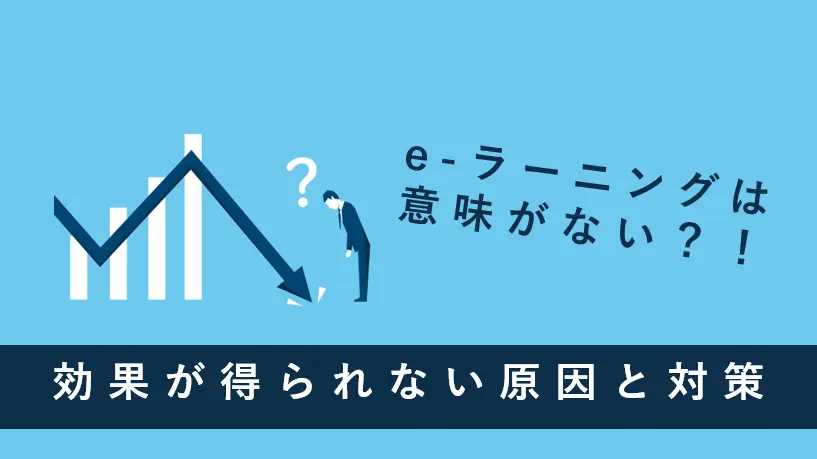


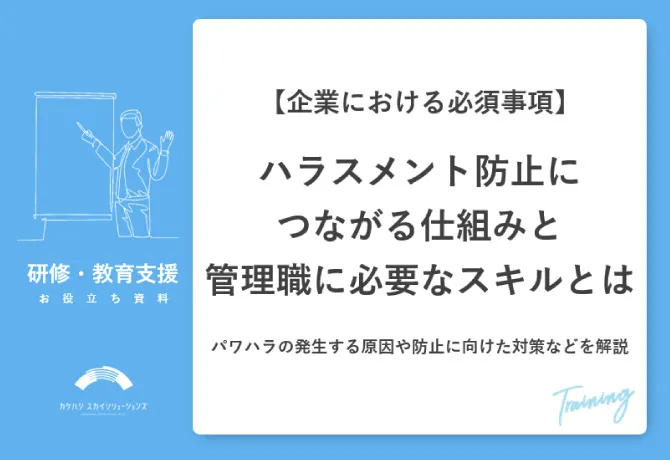
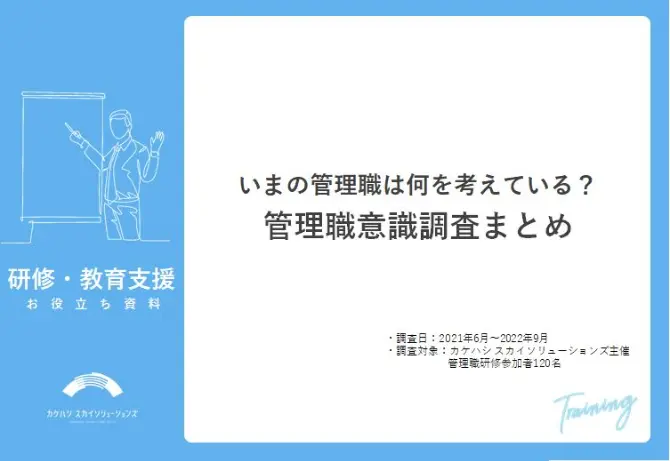

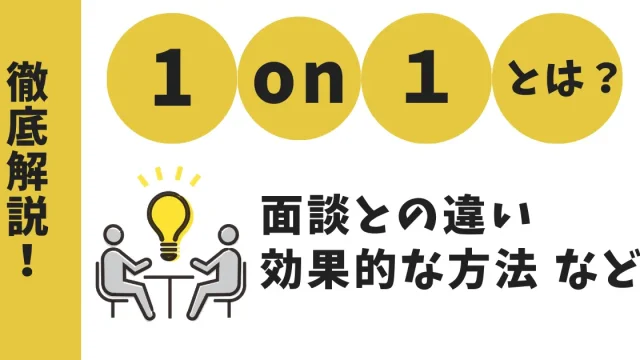
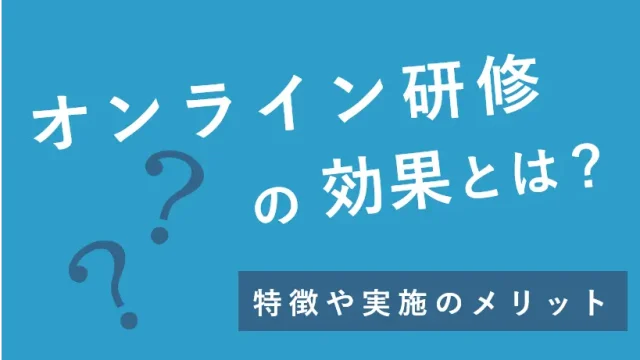
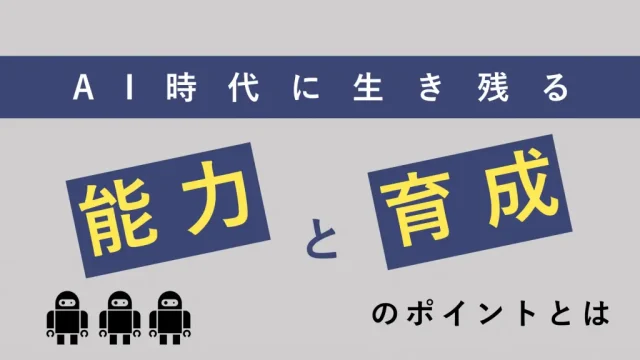
 組織の力を最大化する育成のポイントガイドブック
組織の力を最大化する育成のポイントガイドブック 
 離職防止につなげるオンボーディング活用ガイドブック
離職防止につなげるオンボーディング活用ガイドブック 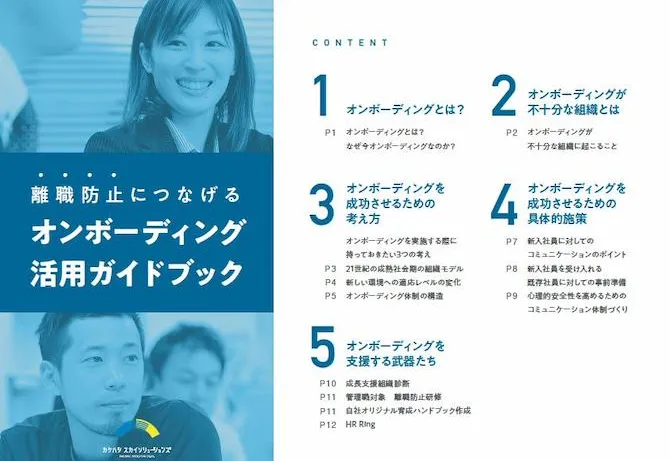
 2024年新入社員意識調査まとめ
2024年新入社員意識調査まとめ