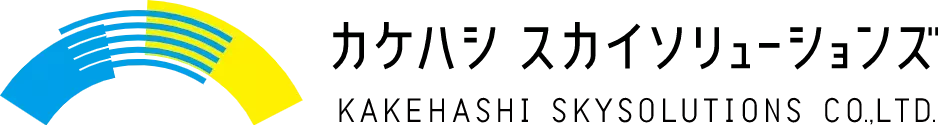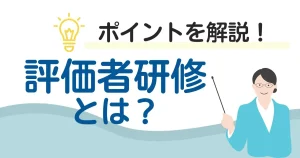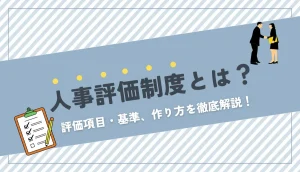評価の目的と評価者の役割、原理原則を再確認し、評価者としてのマインド・スキル向上を目指す研修

対象|評価者(管理職)
近年人気の研修プログラムです。人事評価制度を適切に運用するために、評価者同士で“評価の目的と評価者の役割”について共通認識を持ち、すり合わせておくべき点を明らかにする研修です。
よくあるお悩み
■部下や後輩それぞれを深く知る必要性を感じていない
■部下や後輩のモチベーションが上がるポイントをつかめていない
■部下や後輩が安心して話せる場と関係性をつくることができていない
■育成方法や働きかけ方、アプローチ方法のバリエーションが少ない
評価者研修の目的
評価の目的と評価者の役割について、評価者間で共通認識を持つ
評価は、組織全体の目標達成や社員の成長に直結する重要なプロセスであり、これを正確かつ公平に運用するためには、評価者全員が評価の目的と評価者としての役割について明確な共通認識を持つことが不可欠です。本研修は、評価が単なる業務の一環として行われるものではなく、育成の一環としてメンバーの中長期的成長を目指す研修です。 また、評価を通じて社員の努力を適切に認めて育成につなげるためには、評価者自身が自らの責任を正しく理解し、役割を果たすことが求められます。評価者間で評価基準や評価の運用方法について具体的にすり合わせる場を設けることで、評価に対する一貫性と透明性を高めることを目指します。このすり合わせによって、評価に関する曖昧さや不公平感を解消し、社員に信頼される評価体制を構築します。結果として、全ての評価者が共通の価値観と認識のもとで評価を行い、組織全体の成長と一体感を促進することが目的です。
被評価者の成長に繋がる評価をするために必要なスキルを身に付ける
評価者は単に評価をつけるだけの役割ではなく、社員の成長を支援し、組織全体のパフォーマンスを向上させる重要な担い手です。本研修では、評価の目的や原理原則を改めて整理し、評価者として持っておくべき意識と知識を再確認します。 評価の目的が社員の成果を正しく把握し、適切なフィードバックをおこなうことにとどまらず、潜在能力を引き出し、成長を促すものである点を再認識します。また、評価を公平かつ透明性のあるものとするために、評価者自身が持つバイアスやエラーの傾向を理解し、これを最小化するための具体的な方法を学びます。 さらに、評価結果を効果的に活用するためには、評価面談での適切なコミュニケーションが重要です。この研修を通じて、部下との信頼関係を強化し、評価の質を高めるためのスキルを習得します。評価者としてのマインドセットを再構築し、実務に直結するスキルを身につけることで、組織全体の生産性と従業員のエンゲージメントを向上させることを最終的な目標としています。
評価者研修の期待効果
評価の統一理解と透明性向上
本研修を通して、評価の目的と評価者の役割について参加者全員が共通認識を持つことができます。評価は社員の成長を促進し、組織全体の目標達成を支える重要なプロセスであるため、評価者がその意義を深く理解し、一貫した基準で実施することが不可欠です。 また、評価者間で評価基準に対する具体的な認識合わせを行うことで、評価プロセスの透明性が向上し、社員からの信頼を得る体制が整います。これにより、個々の評価がより客観的で公平なものとなり、組織全体としての一体感が生まれることが期待されます。
評価者のスキル向上
研修では、評価を行う際に自らの傾向やエラー(無意識の偏りや思い込み)を理解し、エラーに陥らないために必要な考え方や意識を理解します。 評価は、双方が納得いく目標設定から始まり、日々の関わりや観察に基づくものであり、日常的なマネジメント活動と密接に結びついています。そのため、評価者自身が日々の関わりの重要性を理解し、日常的なフィードバックや観察を活用できるようになることが期待されます。さらに、評価面談における有効な質問の方法を習得することで、社員が主体的に成長を考えるきっかけを与え、双方にとって有益なコミュニケーションを実現します。 このように、評価者のスキルとマインドセットを向上させることで、組織全体の評価プロセスがより質の高いものとなることが期待されます。
評価者研修のカリキュラム概要
Section1
評価の目的と評価者の役割とは
▼Activity 評価者の役割とは
何のために評価をするのかを改めて考える中で「目標設定及び評価とは、被評価者の成長(育成)のために行うもの」であり、「評価者は育成者の一人」であるという共通認識を持つ。

Section2
評価項目の具体的な行動に関するすり合わせ
▼Activity:評価体感ワーク
グループで3役(本部・親方・職人)に分かれ、それぞれの役になりきり、任務=タワー建設を遂行。
作戦会議・実施を2ターム実施の上、職人評価をつけていく。その後、評価結果と理由を共有。
それぞれの立場で評価をつける/つけられる体感を通して、「納得のいく評価」にするために押さえておくべきポイントを理解する。
▼Activity 評価基準の具体化(個人・グループ・全体ディスカッション)
被評価者の成長を促すための「人材育成・評価の基本プロセス」を理解したうえで、 自社内のいずれかの評価項目について、「日々の業務において具体的にどのような 場面でどのような行動・発言をしていればGoodなのか(良い評価になるのか)」を1つずつ言葉にし、共有することで、評価に携わる関係者同士の基準値をすり合わせていく。

Section3
評価に活かせる ”日々のかかわり” について考える
▼Activity 日々の観察memo
評価者として被評価者と日々の関わりを持つ目的を考えたうえで「日々の関わりを持つ際のポイント」を理解し、被評価者に関する「日々の観察memo」の記入を通して自身の現状を把握する。
▼Activity 日々の観察ポイント
「日頃からどのような情報をメモしておくと評価の際に役に立つか」をグループで話し合い、解説を通して、日々の観察に役立つヒントを持ち帰る。

Section4
評価面談スキルを磨く
▼Activity 評価面談ロールプレイング or 質問トレーニング
評価面談のゴール、流れ、ポイントを理解したうえで、実際の評価を題材に、 ロールプレイングを行う。 ※評価面談の回数(一次、二次)や具体的なスキルが何かによって、 トレーニングの内容は随時チューニングしております。 ※条件として面談のロールプレイング

所要時間
カケハシの評価者研修のこだわりポイント
納得感のない評価は、従業員のモチベーション低下、ひいては人材の流出に繋がります。
人事評価に不満を持つ従業員の割合は55.5%、不満の最多は「評価基準の不明確さ」の48.3%(※1)です。納得感のない評価は、従業員のモチベーション低下、ひいては人材の流出に繋がります。本研修は「被評価者の成長を促す適切な評価」をするために、評価者が評価の目的や自身の役割、原理原則を再確認し、評価者としてのマインド・スキル向上を目指すプログラムです。
※1)2021年8月「 人事評価の“モヤモヤ”に関する調査」
さらば、やりっぱなし研修 ~行動変容を持続させるための取り組み~
貴社の社員の課題に合わせてカスタマイズが可能です。
ベースとなるプログラムのご用意はございますが、実施の際には貴社の該当社員の課題やご要望をお伺いし、より行動が変わるようプログラムをカスタマイズいたします。まずはお気軽にフォームよりご相談ください。

本研修を受講した受講者の声
常日頃からのコミュニケーションの重要性を改めて認識しました。評価者となる自分を客観的に見るための手がかりも提示して頂けたと思います。
ただ「正しい評価をするため」ではなく、「部下を納得させるため」のコミュニケーション方法であり、評価を伝える側としてとても勉強になりました。
(業種|メーカー 階層|管理職層)
評価に関して、やり方、進め方を細かくロールプレイを交えての研修でしたので、凄く勉強になりました。大事なのは、日頃メンバーとのかかわり方が非常に重要と実感をしております。自社の制度に沿った内容となっており、非常に理解できました。他部署の同じ立場の方とグループ別けがされており、いろいろな考え方が知れてとても参考になりました。
(業種|メーカー 階層|管理職層)
講師の方のこれまでの百戦錬磨の社会経験から学ばれたノウハウを惜しげもなく提供頂き、とても感謝しております。この研修を受けていない状態で、評価面談していたらどうなっていたことか想像がつきません。明朗快活な研修でとても楽しく学ぶことができました。ありがとうございました。
(業種|メーカー 階層|管理職層)
自社の新人事制度について、理解してやってきたつもりではありましたが、この研修を受けさせていただくことにより、人材育成に非常に力を入れている事がわかり、部下の評価の仕方や、自分自身の評価への向き合い方の理解も深まったと思います。
(業種| レジャー・アミューズメント 階層|管理職層)
改めて、個人毎の評価の視点や考え方の違いがわかりました。あとは職歴が増える評価の難しさも、実際に自分より職歴が短いマネージャーの考え方を聞けたのは良い機会となりました。マネージャーとして、ある程度の年数を積んできたので、自分の中での考え方等が固まっている部分はあると思います。再度、広い視野や考え方ができるようにしていきたいです。
(業種| レジャー・アミューズメント 階層|管理職層)
この研修は今までの研修よりためになるし、とてもおもしろいというのが印象的でした。講師の話だけを聞くのではなく、グループディスカッションでいろいろな意見交換も出来たし、様々な考えを聞くことができてとても参考になりました。自身も評価をする立場の上で見直すきっかけになりました。適正な評価をするにはまず評価する側、評価される側が評価基準の設定を理解する必要性があると感じました。
(業種| レジャー・アミューズメント 階層|管理職層)
今回の評価者研修に参加してみて、評価する立場としては自身の考え方が基準では無いという事や、評価対象者を育成するという側面も有るという事が分かりました。
社内でも考課など人を評価する場面も有るので、今後は評価対象者を日頃から観察し、部下を育成するという意識を持って取り組みたいと思います。又、自身が評価される立場になった場合も、良い悪いも含め真摯に受け止め成長に繋げていこうと思います。
(業種| レジャー・アミューズメント 階層|管理職層)
評価は人材育成のための一つということを、この研修を受けるまでは気付かなかったので、それを気付けたことは大きいと思います。
(業種| レジャー・アミューズメント 階層|管理職層)
評価は人事育成のひとつということを気付けたのが、一番大きいと思います。
今まで評価を付ける回数は少ないが、出来てることと出来てないことの確認の意味合いが強く、人材育成という視点は全く無かったです。また自分は評価をつける時、甘めになる傾向があるが、甘めに付けることのメリットやデメリットを教えてもらったことにより本人の為に付けたのに、実際は本人の為になって無い事がわかりました。
今回の研修を受けたことにより、今後の評価の仕方も変わると思います。まずは人材育成という視点を第一に考え、評価対象者とコミュニケーションをはかり、お互いが納得する評価を出すことで、モチベーションアップにも繋がり、信頼関係も築けるものと考えました。
(業種| レジャー・アミューズメント 階層|管理職層)
本研修を利用したお客様の声
これまで評価は成果の確認にとどまっていた印象だったが、研修を通じて人材育成の一環として考える視点を管理職に伝えられたのはよかった。部下とのコミュニケーションが深まり、評価面談の質も向上したと感じています。
(業種| その他サービス 役職|経営者)
評価の基準を明確化することで、チーム全体の信頼関係が向上しました。研修で学んだ評価方法やコミュニケーションを実践し、メンバーからも「納得感がある」との意見が出たことがあります。
(業種|メーカー 役職|人事担当者)
評価に対して部下との認識のズレを減らす方法を学びました。研修でディスカッションを重ねたことで、職場でのフィードバック文化が少しずつ浸透してきているように感じます。評価がより前向きなものになりました。
(業種|サービス 役職|人事担当者)
担当講師に関して
貴社にマッチする講師をアサイン・派遣いたします。
当日は研修のテーマや貴社のご状況、業界特性に合わせてマッチする講師を派遣致します。また、「受講者とコミュニケーションを取りながら進めてほしい」「厳しく指導してほしい」といった貴社からのご要望に合わせて、講師派遣はもちろんのこと、研修当日の雰囲気づくりにもこだわります。

よくあるご質問
- この研修はどの層の社員を対象にしていますか?
-
以下のような社員におすすめです。
・新たに評価者となる管理職やリーダー(新任マネージャー、課長・部長、チームリーダーなど)
・既存の管理職・評価経験者
・将来的に評価者となる候補者(次世代リーダー、昇進候補者)
など、組織の評価の精度を高め、部下の成長を促進することが役割となる社員の方々にご受講をおすすめしております。
- 企業文化や業界特有の課題に合わせて、研修内容をカスタマイズすることは可能ですか?
-
可能です。プログラムは貴社に合わせたカスタマイズを必ず行うようにしております。
ご発注前に貴社の課題をお伺いして研修内容の内容のご提案をいたしますので、ぜひ貴社の目指す姿や課題をお聞かせください。行動が変わる最適なコンテンツをご提案いたします。
- オンラインツールを活用したフォローアップやコミュニケーション支援はどのようなものがありますか?
-
eラーニングを活用した事前学習付きのプログラムや研修受講後、職場での実践と振り返りを共有し合うアプリ(自社開発)などを組み込んだプログラムなどもご提案が可能です。
ぜひフォローアップやコミュニケーション支援について、ご要望をお聞かせください。
- 対象者が研修に積極的に参加し、学びを実務に活かすためのモチベーション向上策は何かありますか?
-
「やり方(How)」をお伝えする研修は多いかと思いますが、受講者に主体的に学んでもらうためには「何のために学ぶのか?なぜ必要なのか?(Why)」 を伝えることが重要であると考えています。
カケハシの研修では、「やり方(How)」はもちろんのこと、学ぶことに対する受講者の納得度を高めるために、「何のために学ぶのか?なぜ必要なのか?(Why)」 を丁寧に扱います。プログラムの中に必ずwhyを理解するパートを組み込むようにしております。 - 業務スケジュールとの兼ね合いで、全評価者が一斉に研修に参加するのは難しい場合はどのようにするとよいでしょうか?
-
ぜひご相談ください。
柔軟に日程やクラスを組み、進行のしやすい研修日程・プログラムをご提案させていただきます。 - 評価者のスキルアップが具体的にどのように業績や利益に寄与しますか?
-
評価者のスキルアップは様々な場面で利益に繋がります。
まず社員の納得度の高い評価が行われることで、社員は自身の努力や成果が正当に認められていると感じ、モチベーションが向上します。その結果、業務への意欲が高まり、生産性の向上や離職防止につながります。
また、評価者が効果的なフィードバック技術を習得することで、社員は自身の強みや改善点を明確に理解し、成長を加速させることができます。そうすることで、日々の業務の質が向上し、組織全体のパフォーマンスも向上していきます。評価者が適切な目標設定の方法を学び、部下の成長を支援できるようになることは個人の目標達成だけでなく、組織全体の目標達成にもつながると言えます。
このように、評価を通じた適切な人材育成が行われるようになることで、働く社員のモチベーション向上、業務の質の向上、目標達成の支援へとつながり、最終的には業績や利益の向上に大きく寄与すると考えます。 - 申込から研修実施までの流れについて教えてください。
- ご発注をいただいた後、詳細コンテンツ開発のためのヒアリングをさせていただき、ご相談、ご提案をさせていただきます。研修実施後は受講者の方のフィードバックに伺います。
- 相談してから最短どのくらいで研修実施できますか?
- まずご相談をいただき、貴社のご状況を詳しくヒアリングさせていただき、研修内容のご提案をさせていただきます。その後ご発注いただいてから約2ヶ月間、詳細コンテンツ開発期間を頂戴しますので、ご相談いただいてから最短2ヶ月が目安です。
評価者研修の費用
- 費用
- 費用や詳細のプログラム内容については下記問い合わせボタンより詳細をお尋ねください。