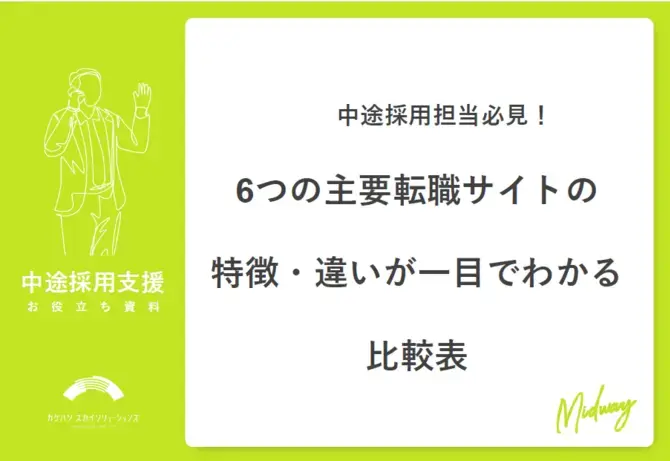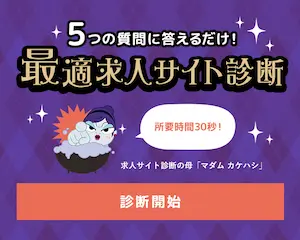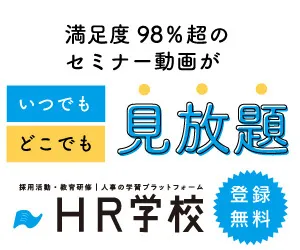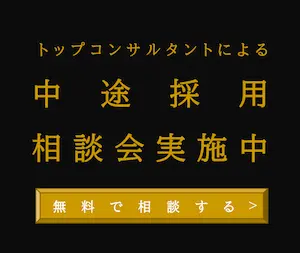近年、人材の採用に課題を抱える企業が多い中、採用活動にマーケティングの手法を取り入れた「採用マーケティング」に注目が集まっています。
今回の記事では、採用マーケティングの基本的な考え方や、導入するメリット、採用力強化につながるポイントを解説します。
目次 [非表示]
採用マーケティングとは何か?
 採用マーケティングとは、ビジネスにおけるマーケティングの概念と手法を採用活動に取り入れることを指します。
採用マーケティングとは、ビジネスにおけるマーケティングの概念と手法を採用活動に取り入れることを指します。
一般的なマーケティングとは、顧客を理解しニーズを満たす製品を作る、またはターゲットとなる層に自社製品やサービスを認知してもらう活動のことです。
採用マーケティングでは、「企業が理想とする人材のニーズを把握し、待遇や職場環境などを整える」「採用ターゲットとなる層に認知を広げ、興味関心を促す」ことを戦略的に実践し、採用成功に導きます。
マーケティングで用いられる考え方や戦略は採用活動にも効果的で、近年採用マーケティングを重要視する企業が増えています。
採用マーケティングと採用ブランディングの違い
 採用マーケティングと併せて語られることが多い言葉に「採用ブランディング」があります。
採用マーケティングと併せて語られることが多い言葉に「採用ブランディング」があります。
採用ブランディングとは、自社のあり方やカルチャーを対外的かつ継続的に発信し、求職者に企業イメージを狙い通りのブランドとして定着させていくことです。
採用ブランディングは、自社のイメージを構築していくためのプロセスとも言えます。
一方採用マーケティングは、採用活動成功のため、どの層にどんな手法でアプローチするのかを考える取り組みです。
また、採用マーケティングでは、求職者の動向だけではなく、同業他社などとの比較といったように相対的に自社をとらえることも大切です。
採用には企業の持つブランドイメージも大きく影響するため、採用ブランディングは、採用マーケティングとも密接に関わっています。
採用マーケティングが重要とされる背景とは?

採用マーケティングが重要視されている背景とは何でしょうか。詳しく確認してみましょう。
労働人口の減少
少子高齢化による労働人口の減少が進み、採用市場では人手不足が深刻化しています。
総務省の「令和4年情報通信に関する現状報告の概要」によると、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少の一途をたどり、2030年には6,875万人に減少すると見込まれています。
労働人口が減少する中、企業が求める人材要件は高度化しており、即戦力となる優秀な人材の獲得が難しくなっているのが現状です。
このように、企業が「選ぶ側」ではなく「選ばれる側」へとシフトした結果、転職顕在層のみならず転職潜在層へも対象を広げるべく、採用マーケティングが注目されるようになりました。
(参照:総務省「令和4年情報通信に関する現状報告の概要:第1節 今後の日本社会におけるICTの役割に関する展望」)
採用手法の多様化
インターネットやSNSの発達によって、一昔前の採用市場と比較して採用手法が多様化しています。
これまでの採用手法は、紙媒体・人材紹介・就活サイト・転職サイトが一般的でしたが、近年では、ダイレクトリクルーティング・リファラル採用・アルムナイ採用など、さまざまな採用チャネルが生まれています。
また、コーポレートサイトやブログ、SNSなどを使った採用情報の発信も不可欠な時代になりました。
採用手法の多様化によって、企業はこれらの採用手法を駆使して自社の求める人材へアプローチしなければならず、その運用方法や訴求方法などの違いを理解した上で採用戦略を立てる必要があるのです。
自社の求める人材へ的確にアプローチして獲得するための手段として、採用マーケティングの重要性が高まっています。
働き方に対する価値観の多様化
近年、ライフスタイルの多様化に伴って、働き方に対する価値観の多様化も進んでいます。
求職者が企業に求める価値観は、かつてのように企業の知名度や安定性、高い給与だけでなく、やりがいや勤務体系に対する柔軟性、カルチャーマッチといった要素も重視されるようになりました。
その中で企業は、自社の社風や働き方、社会的役割などをわかりやすく伝えるためにもコンテンツ化して、求職者へ周知していかなければなりません。
企業がほしい人材へと的確に発信するための手段として、採用マーケティングが不可欠なのです。
情報発信により求職者の企業理解を深められるため、「社風が合わなかった」「業務内容が思っていたのと違う」などといった入社後のミスマッチによる早期離職を防止できるメリットもあります。
採用マーケティングのターゲットとなる層は?
 採用マーケティングでは、転職顕在層だけでなく転職潜在層も含めた転職希望者がターゲットとなります。
採用マーケティングでは、転職顕在層だけでなく転職潜在層も含めた転職希望者がターゲットとなります。
この転職潜在層の中には、自社の社員やアルムナイ(退職者)、過去不採用になった候補者や内定辞退者などの選考参加者もターゲットとして含まれます。
以下では、採用マーケティングにおけるターゲットとなる層についてご紹介します。
幅広い層にアプローチすることで、自社の求める優秀な人材確保を目指しましょう。
自社の社員
採用マーケティングにおいて、自社の社員もターゲットの一つです。マーケティングの観点で「社員=既存顧客」とみなし、戦略上重要な位置づけとなります。
自社の社員がいきいきと働ける環境を整備し、エンゲージメントを高めて帰属意識の醸成を目指します。
自社に愛着を持ってもらうことで、リファラル採用やアルムナイ採用の活性化に加え、結果として社外へのイメージ向上にもつながります。
社員のエンゲージメント向上には、社内コミュニケーションの活性化やワークライフバランスの向上など、社員がストレスなく働ける環境づくりが求められます。
更に、社員のスキルを最大化するため、適材適所への人員配置やキャリア支援、人材育成なども効果的です。
退職者(アルムナイ)
ビジネスでのアルムナイとは、「定年退職以外の離職者・退職者」のこと。
採用マーケティングにおいては、採用候補者、自社の情報発信者、顧客の3つの側面を持っています。
退職した元社員と良好な関係を築くことで再雇用の可能性があるだけでなく、自社での就業経験に基づく信頼性の高いクチコミ発信も期待できます。
また、自社と近い属性の業種に転職した場合など、アルムナイが仲介者となり新たな顧客獲得の機会も生まれます。
外資系企業や国内の大手企業などでも、アルムナイネットワークが活用されるなど注目を集めています。
良質なアルムナイが自社に及ぼす影響は大きく、採用マーケティングの観点からも重要度の高い層と言えます。
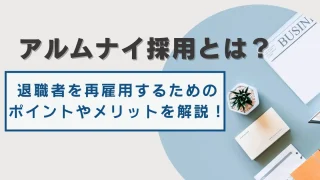
内定辞退者や過去の選考参加者
過去の選考参加者もまた、採用マーケティングの対象です。内定辞退者だけでなく、過去不採用になった選考参加者もターゲットに含めます。
不採用だからとないがしろにしてしまうと、SNSや口コミで「対応が悪かった」などネガティブな発信をされてイメージダウンにつながるリスクがあります。
企業イメージの悪化を防ぐだけでなく、選考参加者はタイミング次第で意向醸成やスキルマッチが可能になり、再度候補者となる可能性もあります。
内定辞退者や最終選考まで残った候補者ほど、マッチング度が高い傾向にあるため、採用マーケティングのターゲットとして適切な対応が不可欠と言えます。
採用マーケティングのメリット
 採用マーケティングを導入するとどのようなメリットがあるのでしょうか。4つのメリットを紹介します。
採用マーケティングを導入するとどのようなメリットがあるのでしょうか。4つのメリットを紹介します。
- ターゲット人材からの応募が増加する
- 潜在的なターゲット層への認知が進む
- 採用コストの削減につながる
- ミスマッチによる早期離職を防止できる
ターゲット人材からの応募が増加する
従来の採用活動に比べ、採用マーケティングのプロセスでは、特定のターゲット人材に刺さるようなメッセージ発信や訴求をおこなうことが特徴です。
そのため、訴求が成功すれば自然に母集団におけるターゲット人材の含有率が増加する傾向にあり、採用の精度を上げることを期待できます。
潜在的なターゲット層への認知が進む
労働人口の減少が確実であることから、企業はこれからも採用難に直面するでしょう。
採用マーケティングでは「この会社で働きたい」と思える情報発信を継続的におこない認知を拡大していきます。
特に潜在層に向けた情報発信では採用情報に限らず、自社のメッセージ、社員、文化、福利厚生といった魅力を多角的に伝えていきます。
ターゲットに転職のタイミングが訪れた際、転職の有力候補先として採用マーケティングは時間差でも効果を発揮することが期待できます。
採用コストの削減につながる
採用マーケティングは、コスト面でも多くのメリットがあります。
採用マーケティングを導入することで、ターゲット人材に特化した訴求をおこない、効果的な採用アプローチが可能になります。
それによりこれまで不要にかけていた広告費などを減らせ、採用コスト全体の削減につながります。
また、マッチング率の向上は離職率の低下につながり、長期的な採用コストや育成コストの削減も期待できるでしょう。
ミスマッチによる早期離職を防止できる
ミスマッチによる人材の早期離職防止も、採用マーケティングをおこなうメリットです。
採用マーケティングでは、採用ターゲット像となるペルソナを設定することでマッチング精度の向上につながります。
情報発信の際には、採用情報以外にも企業理念や代表のメッセージ、社員のインタビューなど自社の強みや魅力を伝えましょう。
応募者の企業理解を深められるため、「思っていたのと違った」などギャップによる内定辞退や早期離職を防ぎ、定着率の向上が期待できます。
採用マーケティングの流れ
 新たに採用マーケティングを導入する企業では、採用活動にマーケティングの思考方法を取り入れ実践していく必要があります。
新たに採用マーケティングを導入する企業では、採用活動にマーケティングの思考方法を取り入れ実践していく必要があります。
ここからは、採用マーケティング導入までの流れを紹介します。
(1)自社の特徴を分析
採用マーケティングをおこなう際は、自社の経営理念や戦略をあらためて見直し、強みや弱みを把握するところから始めます。
例えば強みとしては、特定分野における製品の優位性、福利厚生の充実などが挙げられます。弱みの一例としては、認知度が低いことや若手社員が少ないなども挙げられるでしょう。
自社の特徴を色々な面から客観的に見直し、情報発信することが採用マーティングの第一歩となります。
(2)採用ターゲット選定
マーケティング戦略において重要な要素のひとつがターゲティングです。
採用マーケティングでは、自社が求める人材の特徴を明確にし、アプローチの対象を絞り込みます。
ターゲット設定が曖昧では、施策の効果が出づらく、コストと労力だけが消費されていく事態になりかねません。
採用マーケティングでは、狙う人材に集中的にアプローチすることが重要です。
(3)採用ターゲットのニーズ調査
設定した採用ターゲットがどのようなニーズを持っているかを調査します。
例えばターゲットが求める職場条件は、SNSによるアンケート調査結果やこれまでの採用活動で得られたデータなどから導き出せます。
自社での調査が難しい場合には、外部の採用活動のプロフェッショナルに相談してみるのもよいでしょう。
(4)効果的なアプローチ策を検討
整理したニーズから、ターゲットに響く効果的なアプローチ方法を検討します。
転職活動中の求職者と転職潜在層へのアプローチ方法は異なるため、フェーズごとに響く施策というのは当然変わってきます。
重要なのは「興味関心を強める施策」であり採用結果につながること。自社に最適なアプローチ方法を検討します。
(5)採用施策の実施
採用施策を実施していきながら、日々振り返りをおこない改善点がないかをチェックします。
例えば、「広報に反応がない」「採用ターゲット違うタイプの応募が多い」「辞退者が多い」などの問題が発生することもあります。
データ分析などをおこない原因を究明し、課題を解決するにはどうするべきかを具体的に考えた上で施策を改めて講じていきます。
社会情勢の変化も激しいためPDCAを回しながら、採用マーケティングを継続していきます。
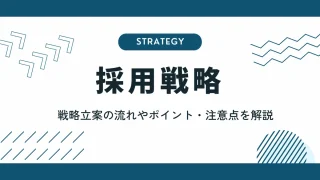
採用マーケティングを成功に導くポイント
 採用マーケティングを取り入れて採用を成功させるためには、いくつか押さえておきたいポイントがあります。
採用マーケティングを取り入れて採用を成功させるためには、いくつか押さえておきたいポイントがあります。
効果的な採用マーケティングをおこなう上で必要な要素について以下で解説します。
採用担当者のマーケティングスキルを磨く
採用マーケティングを成功させるためには、自社の採用活動で得られたデータの分析をおこなう必要があります。
人事の採用担当者は、データから状況や課題を読み解いて戦略に活かすマーケティングスキルを身に付けましょう。
データを計測・分析できる仕組みを作り、その分析をもとに改善を繰り返します。
母集団の数や応募数、面接通過率、内定率、内定辞退率など、各プロセスでのデータを集計・蓄積してそれを分析することで、効果的な採用戦略や施策の企画立案ができるようになります。
既存の採用担当者のリソースが足りない場合は、専属のマーケターを配属するのもよいでしょう。
マーケターの知見を採用活動に活かして、成果の向上を図ります。
フレームワークを活用する
分析にフレームワークを活用するのも、採用マーケティングを成功させるポイントです。
採用戦略を立てるためにはまず自社の分析が重要となります。
企業理念や経営戦略をはじめ、自社の置かれている状況や環境などを適切に分析し、強みと弱みを把握しましょう。
よく使われる思考フレームワークを以下でご紹介します。
自社を分析する際に活用してみてください。
| 3C分析 | 「Customer(顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つの視点から分析して自社の立ち位置や強みなどマーケティング環境を把握します |
| 4C分析 | 「Customer Value(求職者にとっての価値)」「Cost(求職者の負担)」「Convenience(求職者にとっての利便性)」「Communication(求職者とのコミュニケーション)」を分析することで、求職者から選ばれるための採用戦略や採用プロセスを設計します |
| 4P分析 | 「Philosophy(企業理念)」「Profession(事業・業務内容)」「People(人材・文化)」「Privilege(働き方・待遇)」を整理し、自社の魅力を分析します |
| SWOT分析 | 「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」「Opportunity(市場機会)」「Threat(脅威)」の4つの要因から自社が置かれている環境を分析します |
採用ファネルを活用する
ファネルとは、マーケティング用語の一つです。
顧客が商品・サービスを「認知」してから「購入」するまでのプロセスを図式化したもののことを指します。
これを採用マーケティングに当てはめ、「入社前」から「入社後」までのプロセスをファネルとして捉え、戦略的な採用活動をおこないます。
求職者の行動を「認知」「興味・関心」「選考・内定」「入社後」の4つに分けて、それぞれのプロセスにおける課題を洗い出して改善を図りましょう。
採用ファネルを活用することで、自社の採用活動を整理することができるため、おすすめです。
社内連携に注力する
採用マーケティングを取り入れて採用活動を成功に導くには、採用担当者だけでなく社内全体での連携が不可欠と言えます。
自社分析やペルソナ設計、採用基準の作成する際には、経営陣や現場社員も巻き込んで進めていきましょう。
社内へのヒアリング・アンケートの実施や、面接・選考・クロージングへの参加など、他部署の協力を得ることで、ミスマッチによる早期離職を防ぐ効果も期待できます。
採用マーケティングの成功事例
 採用マーケティングの成功事例として、専門メディアを立ち上げ運営した例をご紹介します。
採用マーケティングの成功事例として、専門メディアを立ち上げ運営した例をご紹介します。
スマートフォンアプリの開発や運営をおこなう情報サービス企業A社では、採用ブランディング確立のための専門メディアサイトを作成しました。
事業内容の紹介や販促などを目的としたコーポレートサイトとは別に、採用候補者に向けて企業風土や採用情報を発信するオウンドメディアを運営しています。
採用に特化した情報を一か所に集約したことで、求職者側のCXも向上する上、求職者とのコミュニケーション効率も改善されました。
応募前や入社前に情報共有ができた上で、選考や入社をスムーズに迎えられるのもメリットと言えます。
まとめ
 人材獲得競争が難しい状況にある中、採用マーケティングの思考を取り入れていくことは重要です。
人材獲得競争が難しい状況にある中、採用マーケティングの思考を取り入れていくことは重要です。
自社での採用マーケティングが難しい場合には、専門知識のある採用コンサルティングサービスへ協力を依頼し、戦略を構築していくこともできます。
今回の記事を参考に自社の採用活動に採用マーケティングを導入してみてはいかがでしょうか。
開催中の無料セミナー
貴社の採用要件、時代錯誤かも…!
ここを直せば応募が来る、求人票の見直しセミナー
開催日時:
2025年4月16日(水)10:00-10:30
まだ無駄なコストを払いますか?
キャリア採用のコストを見直し、賢く採用する方法
開催日時:
2025年4月24日(木)10:00-10:30
転職フェアへの出展を検討中の企業様限定
貴社は出るべき?出ないべき?
転職フェアで採用がうまくいく企業の共通点
開催日時:
2025年4月25日(金)10:00-10:30
おすすめのお役立ち資料
中途採用の他、各分野のお役立ちコラムを公開中
中途採用の知恵袋の他、新卒採用の知恵袋、社員研修の知恵袋、離職防止の知恵袋を運営しています。ぜひ合わせてご覧ください。
 |
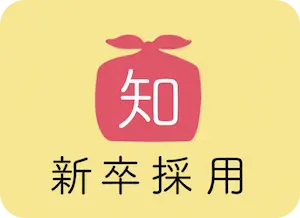 |
 |
 |

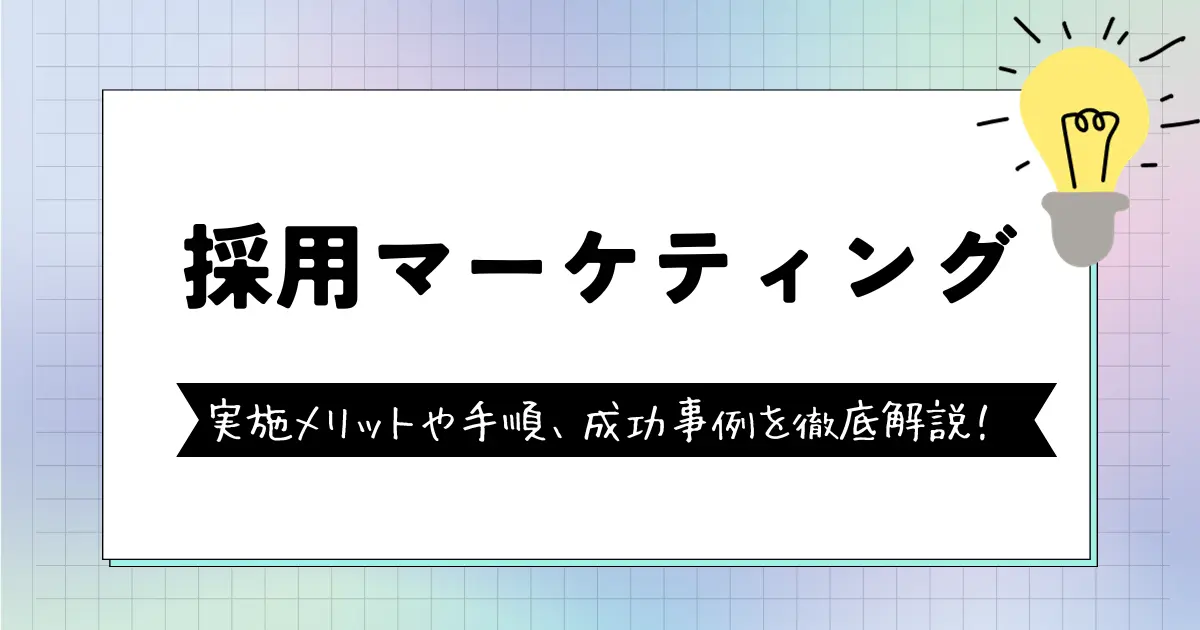
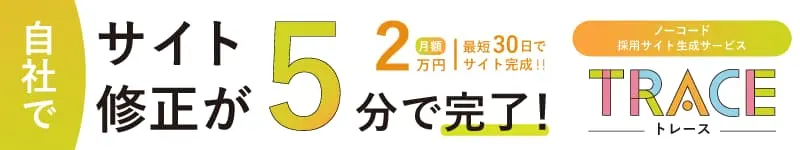
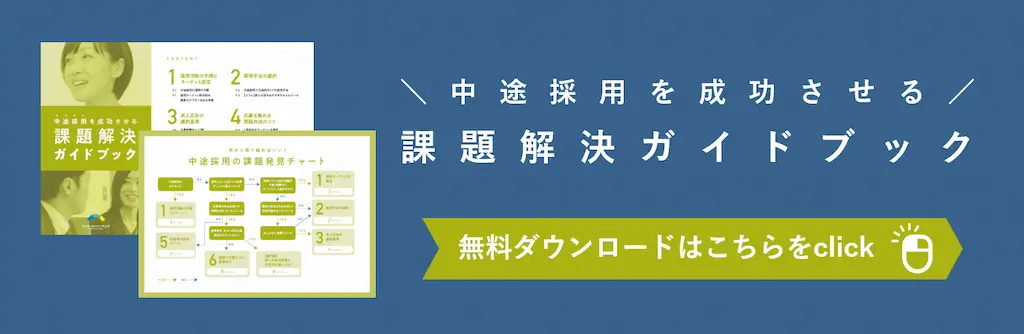
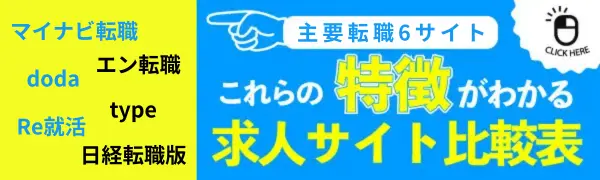
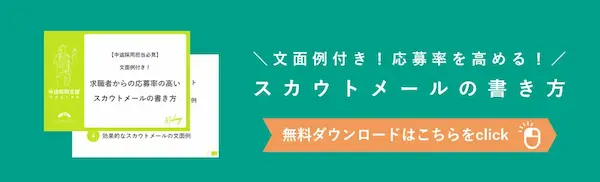
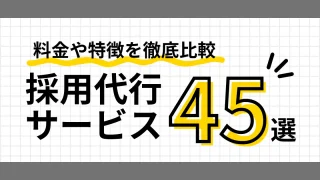
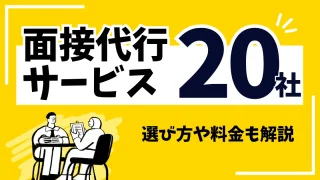
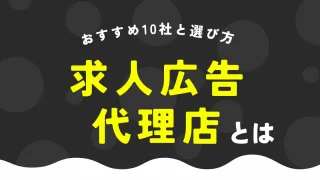
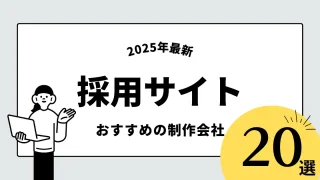
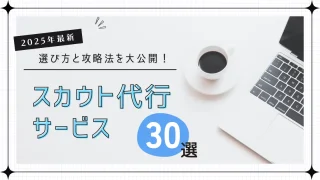
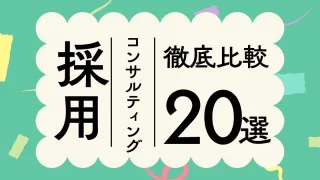
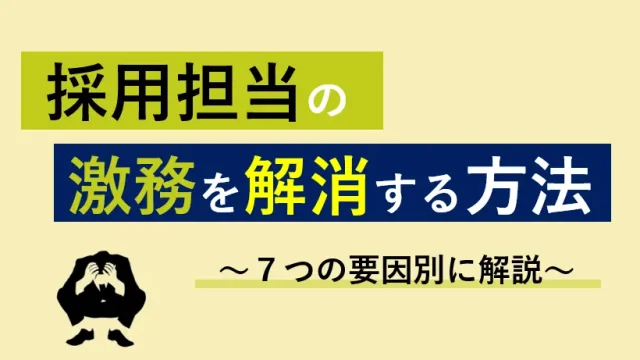
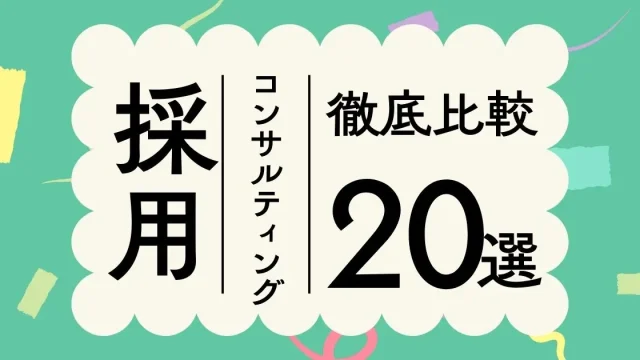
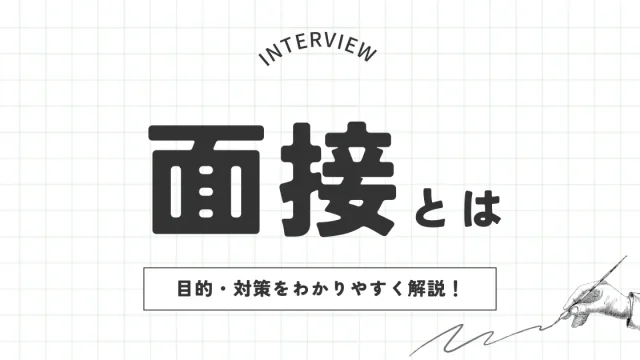
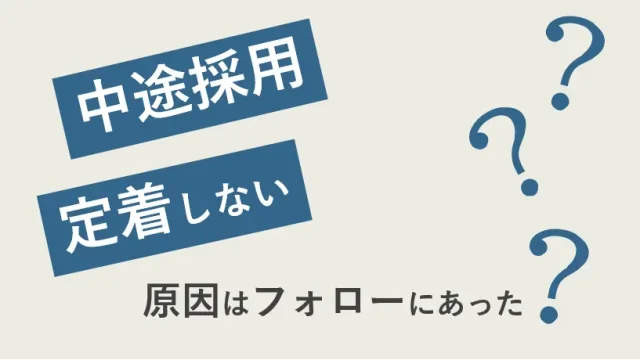
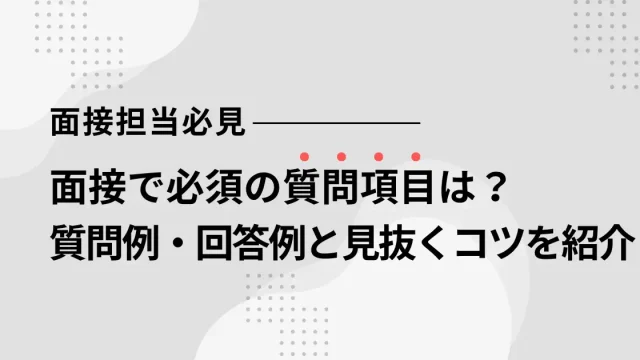
 ざんねんな求人票図鑑
ざんねんな求人票図鑑 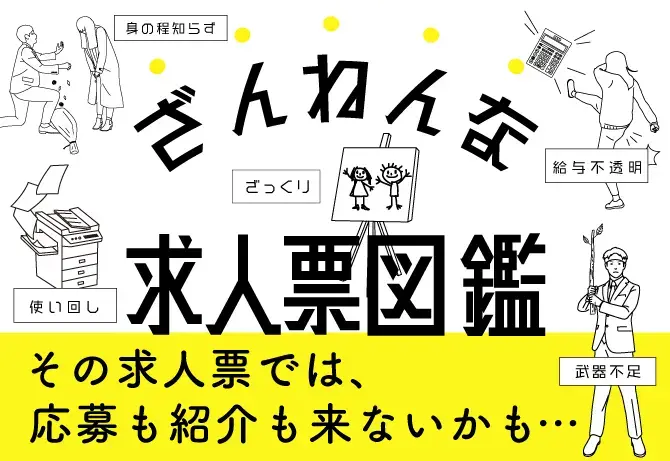
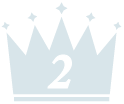 中途採用を成功させる課題解決ガイドブック
中途採用を成功させる課題解決ガイドブック 
 6つの主要転職サイトの特徴・違いが一目でわかる比較表
6つの主要転職サイトの特徴・違いが一目でわかる比較表