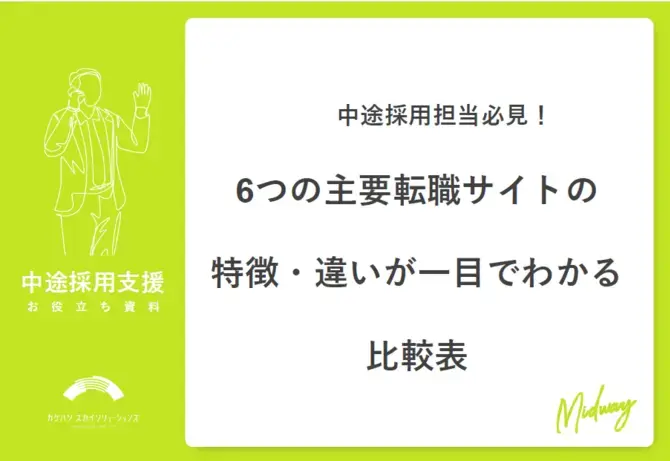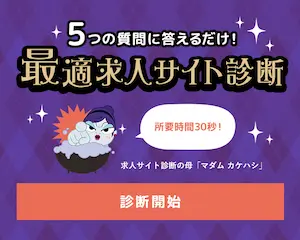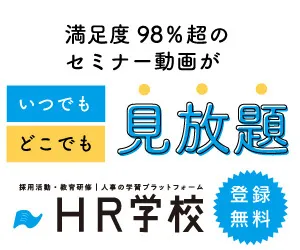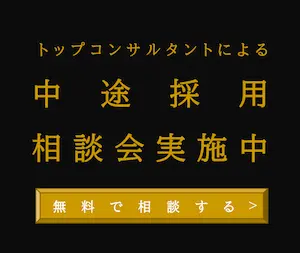採用方法が多様化する中、企業の採用担当者は「どの方法を選べばよいかわからない」「トレンドの採用方法がわからない」など、悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
この記事では、代表的な13種類の採用方法とトレンド、採用方法の選び方と成功させるためのポイントについてご紹介します。
採用方法・手法の種類13選
 採用方法・手法には様々な方法があり、それぞれに特徴が異なるため、自社のターゲットに適したものを選ぶ必要があります。
採用方法・手法には様々な方法があり、それぞれに特徴が異なるため、自社のターゲットに適したものを選ぶ必要があります。
ここでは主な採用方法をご紹介しますので、参考にしてください。

(1)求人広告
| 特徴 |
|
| メリット |
|
| デメリット |
|
| サービス例/依頼先 |
|
求人広告は、民間企業が運営する「求人情報を掲載する媒体」です。
新聞や雑誌などの紙媒体とWeb媒体の2種類に大別されます。
企業は求人広告媒体に料金を支払って求人広告を掲載し、応募が来るのを待ちます。
インターネットが普及した今、Web媒体は最も多く利用されている主流の採用手法と言えます。
新卒・中途・アルバイト・派遣などの雇用形態別サイトの他にも、エンジニア・専門職など特定のターゲットを対象とした特化型サイトも増えています。
一方、地域密着型の紙媒体は、インターネットをあまり使わないシニア層や地元の求職者へのアプローチを得意としています。
自社の求めるターゲット層によっては力を発揮してくれる手法の一つです。
求人広告は、一度の掲載でより多くの求職者に周知できるのがメリットです。
しかし、掲載には多額の費用がかかる他、掲載期間や掲載できる情報量が限られている点がデメリットとして挙げられます。
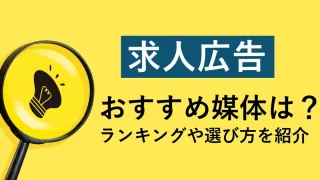
(2)合同企業説明会(転職フェア)
| 特徴 |
|
| メリット |
|
| デメリット |
|
| サービス例/依頼先 |
合同企業説明会(転職フェア)などの各種イベントは、来場した求職者と対面で自社の魅力をアピールできる採用手法です。
一つの会場内に多くの企業が集まるため、自社を知らない求職者にもアプローチでき、認知拡大を図れるほか、企業ブランディングの効果も見込めるのがメリットです。
主に「全業界対象型」「業界特化型」「学部・学科限定型」の3種類に分けられ、参加人数は数十人から1,000人超の大規模なものまで様々です。
自社PRや質疑応答、面接など採用プロセスを一度におこなえるのが特徴。
エンジニアなどの業界特化型では、志望度が高くスキルを持った求職者に出会える可能性が高くなります。
デメリットは、出展料が高い点です。
料金は、出展する日数やブースの大きさなどによって異なります。
限られた日数でどれだけの求職者に興味を持ってもらえるかがカギとなり、費用対効果に注意する必要があります。
さらに、事前準備や当日対応のための工数がかかることもデメリットとなるでしょう。
(3)人材紹介
| 特徴 |
|
| メリット |
|
| デメリット |
|
| サービス例/依頼先 |
|
人材紹介は、人材紹介会社(エージェント)にほしい人材を伝え、それに見合った人材を紹介してもらう方法です。ヒアリングをおこなった上で紹介してくれるため、精度の高いマッチングが期待できます。
人材紹介には、エージェントが抱える人材の中から紹介する「一般紹介・登録型」と、人材を探してヘッドハンティングする「サーチ型」の2種類があり、「一般紹介・登録型」が主流です。
研究者や役員クラスなど採用難易度の高い人材求人の場合、「サーチ型」が多く利用されています。
特定の業界や職種を扱う特化型の人材紹介サービスも増えており、ピンポイントで求めるスキルや経歴を持つ求職者と出会える可能性も高くなります。
また、登録されている人材は、事前に人材紹介会社側が面談をおこなうため、ある程度スクリーニングされた人材を選考できるのが特徴。
面接の日程調整から入社までのやり取りを人材紹介会社が仲介してくれるので、人事担当者の負担軽減にもつながります。
料金体系は、採用成功時に費用が発生する「成功報酬型」が一般的で、相場は採用者の年収の30~40%と比較的高いのがデメリット。
地域や採用条件によっては、企業が求める人材が集まらないケースもあるでしょう。
(4)ハローワーク
| 特徴 |
|
| メリット |
|
| デメリット |
|
| サービス例/依頼先 |
|
ハローワーク(公共職業安定所)は、厚生労働省が運営する職業紹介サービスです。
求職者に向けた職業紹介や職業訓練、雇用対策などの支援を無償でおこなう国の行政機関であり、求人の掲載に原則費用は発生しません。
利用に際して助成金や補助金が支給される場合もあります。
ハローワークは利用者が多く、若い世代から60代以上まで幅広い年齢層の人材へ向けて募集できるのがメリットです。
事業所の管轄となるハローワークで求人を申し込むため、地域採用にも向いています。
しかし、誰でも気軽に応募できるため、応募者の質には偏りがある他、専門スキルを持った人材や即戦力人材の採用には不向きと言えます。
また、ハローワークの求人票は各項目の文字数に制限があり、求める人材についての詳細が記載できないことから、マッチング精度の向上につながりにくいのが難点でもあります。
求人票の作成や面接、選考などの採用業務は企業でおこなう必要があるため、採用担当者に業務負担がかかることもデメリットです。
(5)自社のWebサイト
| 特徴 |
|
| メリット |
|
| デメリット |
|
| サービス例/依頼先 |
|
自社のWebサイト内の採用ページや、採用サイトで求人募集する方法です。
インターネットの普及により、求職者のほとんどが応募前に企業ホームページや採用サイトをチェックしています。
そのため、採用活動において自社のWebサイトに求人情報を掲載するケースは一般的になりました。
掲載情報に制限がないため、写真や動画など求人媒体では伝えきれない情報や求人情報以外の自社の魅力なども、求職者にアピールできるのがメリットです。
自社採用サイトで求職者が直接応募できるフォームを設けたり、自社が運用しているSNSやYou Tubeチャンネルなど、Web媒体と採用サイトを連携して求職者の志望度を高めたりと、応募促進にもつながります。
求人広告媒体など外部サービスを利用するよりも、比較的低コストで運用できる一方で、コンテンツの更新などの工数がかかる点に注意が必要です。
また、ターゲット層は「自社を知っており、興味を持っている人」のみとなり、不特定多数へのアプローチが難しいといったデメリットもあります。
(6)リファラル採用
| 特徴 |
|
| メリット |
|
| デメリット |
|
| サービス例/依頼先 |
|
リファラル採用は、自社従業員からの紹介により人材を獲得する採用手法です。
自社の業務内容や社風を理解した従業員が知人や友人など知り合いを紹介するため、他の採用方法と比較すると、採用コストを抑えることができます。
現従業員による紹介で人材を募ることから外部サービスを使う必要がなく、コスト削減にもつながるでしょう。
紹介後は、通常の採用と同じプロセスで選考をおこないます。
不特定多数から募集するよりもミスマッチが少なく早期離職防止が期待できるというメリットもありますが、大人数の採用には向いていません。
また、入社後にパフォーマンスが好ましくなかった場合や、何らかのトラブルが生じた場合には紹介者である社員との関係が悪化することもあるため、リスクを想定した工夫が企業側に求められます。
費用は、採用にかかる諸費用の他、紹介者にインセンティブを支払う場合は紹介料が発生しますが、他の方法に比べると安く抑えられる傾向にあります。
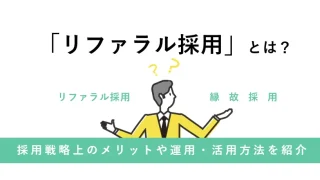
(7)ソーシャルリクルーティング(SNS)
| 特徴 |
|
| メリット |
|
| デメリット |
|
| サービス例/依頼先 |
|
ソーシャルリクルーティングとは、企業が運用するSNSを活用したダイレクトリクルーティング手法の一つです。
外部サービスを介さずに企業が求職者に直接アプローチできるのが最大のメリットと言えます。
X(旧Twitter)やInstagram、FacebookといったSNSから応募者にコンタクトを取る他、自社の採用情報を発信して認知拡大も図れます。
SNSを運用する人件費はかかりますが、SNSの利用料は基本的に無料のため導入のハードルは低く、採用サイトや求人媒体よりもコストを抑えられます。
SNSの利用率は年々上昇傾向にあり、特に若年層へのアプローチ手段として多くの企業が注目しています。
高い拡散性により、転職潜在層の獲得にも効果を発揮する他、内定辞退の防止策としても役立ちます。
しかし、効果的な採用活動につなげるためには、定期的かつ長期的な運用が求められます。
(8)大学や専門学校の就職課
| 特徴 |
|
| メリット |
|
| デメリット |
|
| サービス例/依頼先 |
|
大学や専門学校など教育機関の就職課(就職支援センター・キャリアセンター)を利用して、掲示板や学内システムに求人を掲載する方法もあります。
学部や専門分野を指定した募集もできる他、学校の特色から学生の特徴が判断しやすいのがメリットです。
ただし、どのくらいの応募数があるか予測が難しく、メインの採用手法には向きません。
また、複数の大学に掲載する場合は手間がかかる上、学校によっては掲載を断られる可能性もあるのがデメリットとして挙げられます。
(9)インターンシップ
| 特徴 |
|
| メリット |
|
| デメリット |
|
| サービス例/依頼先 |
|
学生が企業で実際に働くインターンシップも採用方法の一つとして広まりつつあります。
選考活動開始よりも前に企業で話を聞いたり、仕事を体験してみたりできる制度です。
インターンの期間は数日から数ヵ月と会社によって様々あります。
企業側は学生の適性を見極められ、学生側は仕事内容や企業風土などの相性を見極められることから、採用後のミスマッチ防止に高い効果が期待できます。
一緒に働くことで、採用選考だけでは見えにくい学生の人柄や特徴などが把握しやすいため、実施する企業が増えています。
メリットが多い一方、インターンシップの実施には指導する人員や場所の確保、関係各所との調整など学生を受け入れる体制の構築が必要となり、非常に労力がかかります。
受け入れたインターン生の能力によっても現場の負担が増してしまう可能性もあるなど、デメリットもあることを忘れてはいけません。
(10)ヘッドハンティング
| 特徴 |
|
| メリット |
|
| デメリット |
|
| サービス例/依頼先 |
|
ヘッドハンティングとは、ダイレクトリクルーティングの一種で、経営幹部や専門職など優秀な人材を他社からスカウトする採用方法のこと。
ハイクラス人材は、転職サイトなど通常の採用活動で見つけるのは困難なため、専門のヘッドハンティング会社や転職エージェントに依頼する必要があります。
優秀な人材を採用できる一方、他の方法と比較して費用が高いのがデメリットと言えます。
ヘッドハンティングには、主に「エグゼクティブサーチ型」と「登録型」の2種類があり、サービス会社によって対応できるターゲット層や人材獲得における流れが異なるため、選定する際には注意しましょう。
また、似た言葉に「引き抜き」がありますが、こちらは仲介会社を挟まず自社で人材を探して採用する手法です。引き抜く人材の階層や能力に定義はないのが特徴です。
(11)アルムナイ採用
| 特徴 |
|
| メリット |
|
| デメリット |
|
| サービス例/依頼先 |
|
アルムナイ採用は、過去に自社で働いていた人材(アルムナイ)を再び採用する方法です。
企業風土を理解しており、即戦力となる人材を採用するのに向いているでしょう。
企業から直接声をかけたり、候補者から再度応募があったりするケースが多く、採用コストや手間がかからないのが特徴です。
ただし、アルムナイとの関係を維持するためには、定期的にコミュニケーションを取る必要があります。
自社での勤務経験があることから、ミスマッチが起こりにくく、即戦力となる人材を採用できるため、入社後の教育コストも削減できるのがメリットです。
対象となる人材が限られるため大量採用には向かないことに加え、他社で勤務している場合には採用につながりにくい点は注意しておきましょう。
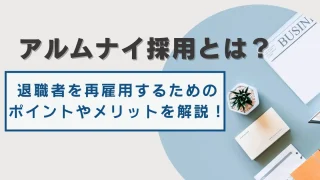
(12)ダイレクトリクルーティング
| 特徴 |
|
| メリット |
|
| デメリット |
|
| サービス例/依頼先 |
|
従来の転職サイトのように、求職者からの応募を待つ受動的な採用ではなく、企業が能動的に求職者にアプローチする採用方法をダイレクトリクルーティングといいます。
具体的には、企業自らがSNSや人脈、ダイレクトリクルーティングサービスなどを活用し、ほしい人材をスカウトする方法です。
企業自らが求職者に対してアプローチするため、採用コストを抑えることができます。
前述した「ソーシャルリクルーティング」「リファラル採用」「ヘッドハンティング」もダイレクトリクルーティングの一種です。
近年では、労働人口の減少により、人材獲得競争が激化しています。
転職顕在層だけでなく転職潜在層にもアプローチできるダイレクトリクルーティングは、攻めの採用手法として取り入れる企業が増えています。
ほしい人材にだけアプローチすることで効率的な採用活動が望める一方、人材一人ひとりに対して個別に対応しなければならないため、採用担当者にとって大きな負担がかかるケースも少なくありません。
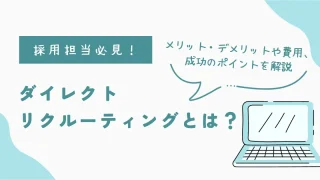
(13)人材派遣
| 特徴 |
|
| メリット |
|
| デメリット |
|
| サービス例/依頼先 |
|
人材派遣は、人材派遣会社が雇用する派遣社員を自社に派遣してもらうサービスです。
人材派遣会社に登録している求職者の中から自社にマッチした人材を探し出すため、効率よく求める人材に出会えます。
他の採用方法と比べるとコストは高めですが、成果報酬制が基本となるため、採用にならなければコストがかかることはありません。
雇用期間を決められるため、「繁忙期のみ」や「育児休暇中のみ」など必要なときに必要な人数を採用できます。
また、人材派遣は、一般的に採用までのスピードが早いのと、必要なスキルや経験を持っている人材がほとんどのため、急を要する人員補充に適しています。
即戦力としての活躍が期待できるのもメリットです。
派遣される人材は、人材派遣会社と雇用契約を結んでいるため、給与の支払いや社会保険の手続きなど契約にかかる煩雑な業務を削減できます。
企業が人材派遣会社に支払う派遣料は、派遣会社ごとに異なり、専門性の高い人材であるほど費用は高くなります。
しかし、どれだけ優秀な人材が派遣されたとしても、自社の社員ではないため雇用期間が過ぎれば辞めてしまいます。ノウハウが蓄積されにくいのもデメリットと言えます。
企業が人材派遣を利用する場合は、あくまで補助的に活用することをおすすめします。
近年の採用方法のトレンドは?
 少子高齢化による人手不足が深刻化する中、近年では有効求人倍率が1倍を超えて緩やかな上昇傾向にあり、売り手市場の傾向が強まりつつあります。
少子高齢化による人手不足が深刻化する中、近年では有効求人倍率が1倍を超えて緩やかな上昇傾向にあり、売り手市場の傾向が強まりつつあります。
コロナ禍で止まっていた採用活動を再開する企業が増えたことも影響し、競合他社との人材獲得競争の激化は避けられません。
母数の減少に伴い、採用市場の動向は従来の「待ち」の採用ではなく、企業側から積極的に働きかける「攻め」の採用手法を取り入れる企業が増えつつあります。
そのため、優秀な人材の採用には様々な採用方法を用いたアプローチ方法が求められています。
具体的には、今後ダイレクトリクルーティングやリファラル採用、ソーシャルリクルーティングなどの活発化が予想されます。
その入口として、「カジュアル面談」「ミートアップ」など新たな候補者との接触機会が注目されています。
これまでの手法
2000年代の主な採用手法は求人サイトでした。以降は、多くの種類の求人サイトが増え、各企業が様々なサービスを提供しています。
正社員採用を目的としたサイトや、アルバイト採用の掲載が多いサイトの他、地域密着型、女性が働きやすい職場特化型、派遣会社専門、特定の職種/業種特化型など、求人サイトの多様化が加速しました。
様々な求人サイトから掲載先や閲覧先を選択できるようになった一方で、求職者や掲載企業が各サイトに分散し、それぞれの効果が低下する傾向も見られています。
2010年代後半には、各求人サイトを集めて検索できる求人検索エンジンも登場した他、ダイレクトリクルーティングなども普及しました。
採用難の近年において、人材不足に陥らないためにも、企業の採用担当者は最新のアプローチ方法を知っておく必要があると言えます。
注目を集める5つの新たな採用方法を以下でご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
(1)カジュアル面談
カジュアル面談とは、企業と参加者がリラックスしながら対話し、相互理解を深める機会のことです。
一般的に、候補者が応募するかどうかを決定する前におこなわれますが、場合によっては、選考中におこなわれるケースもあります。
選考前のカジュアル面談では、参加者の自社への好感度を高め志望度を向上させるよい機会となります。
名前の通り、カジュアルな環境でおこなわれることが多く、履歴書や職務経歴書は原則不要とされています。
コロナの影響もあり近年ではオンラインで実施されることも増えています。
候補者に対して一方的に質問する通常の面接とは異なり、互いに質問し合うことで双方向の興味づけができるメリットがあります。
企業から求職者に対してカジュアル面談の実施を提案するケースも増えており、面談を受けた結果、応募意欲があまりなかった人が選考に進むことも少なくありません。
通常の選考よりも負担が増える一方、ミスマッチにより起こる「内定辞退」や「早期離職」を防止する効果も高く、導入する企業が増えています。
(2)ミートアップ
ミートアップ(meetup)とは、共通の目的を持った人たちが集まって交流する機会のことです。
もともとは、アメリカの企業が作ったプラットフォーム名でしたが、現在ではこのような交流の場のことを「ミートアップ」と呼ぶようになり、ビジネスでの活用が始まりました。
一般的には、企業がイベントのテーマや日程を告知して、興味を持った人が参加する形式が多く見られます。
ミートアップは採用活動だけでなく、自社のブランディングや認知拡大にも効果を発揮するなど様々な場面で活用されています。
採用活動においては、自社の見学や社員との交流を通して自社を知ってもらい、好感度を高めて応募につなげる役割を担っています。
主な種類として「交流会型」「勉強会型」「説明会型」の3つがあり、職種やターゲットなど目的に合わせて使い分ける必要があります。
ミートアップは、転職潜在層にもアプローチできるのが特徴です。
参加者が後々転職を検討し始める際に、「この企業が好印象だったから受けてみようかな」と一番に思い出してもらえるような魅力的なテーマや内容で開催しましょう。
(3)採用代行
採用代行とは、採用業務の一部、もしくはすべてを外部の代行会社に委託する採用方法の一種です。
採用計画の立案や求職者管理、説明会・面接のスケジューリングから実施まで、様々な採用業務を依頼できます。
採用方法の多様化が進み、採用に関する工数は増える一方です。
代行会社は、最新のデータや蓄積したノウハウを活用し、企業にとって最適な方法で採用活動をおこないます。
採用担当者の負担軽減ができるだけでなく、採用市場の動向や新たな採用手法に精通したプロに業務を任せることで、より優秀な人材を採用できる可能性が高まります。
一方、代行会社の担当者とのすり合わせが不十分だと、認識のズレが生じて採用後のミスマッチにつながる可能性もあるので注意しましょう。
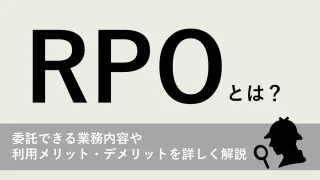
(4)採用ピッチ資料
採用ピッチ資料とは、求職者をターゲットとした会社紹介資料のことです。
ピッチは「短いプレゼンテーション」を意味しています。
応募者が知りたい情報や企業が伝えたいメッセージを、体系的かつストーリーを持たせて作成し、採用活動に用いる方法です。
コロナ禍でオンライン化が進んだことにより、会社説明会や面接のために直接会社に訪問してもらえず、企業の雰囲気や文化がわかりにくいことが課題となっています。
加えて、売り手市場により求職者の企業を見る目が厳しくなっていることから、企業のリアルをオンラインで見れるコンテンツが求められています。
企業サイトなどに載っている会社紹介資料は通常、株主や投資家、顧客など様々な層をターゲットにしていますが、採用ピッチ資料のターゲットは求職者です。
そのため、働くことをイメージしやすいよう、社風や社員紹介、待遇などの情報を多く盛り込んでいます。
最近では、文章や写真よりもより多くの情報量を短時間かつわかりやすく伝えられる「採用ピッチ動画」も増えています。
より多くの人に見てもらい、自社に興味を持ってもらうためのツールとして、多くの企業が活用するなど近年注目を集めている方法です。
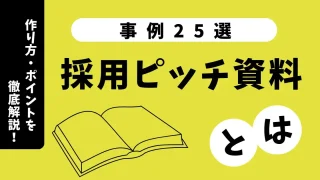
(5)SNSのDM
SNS内で送れるダイレクトメッセージ機能を使って個人にアプローチする方法です。
プライベート用の個人アカウント以外にビジネスアカウントを持つ人も増えており、SNSのDM経由で実際に採用に至ったケースも少なくありません。
終身雇用制度の崩壊により、一つの会社で定年まで働く考え方から、色々な企業で経験を積みながら自分でキャリアを築いていく考え方にシフトしています。
そのため、企業から個人に直接アプローチする方法も効果的と言えます。
SNS上では、個人の発言や考え方が投稿から見えるため、人となりや仕事に対するスタンスが自社とマッチするかどうかも判断できます。
転職を検討している人だけでなく、転職潜在層にも直接コンタクトが取れるため、一度試しにアタックしてみることをおすすめします。
ただし、複数の候補者とリアルタイムでコミュニケーションを取る場合、候補者一人ひとりに丁寧かつ誠実な対応を心がけることが重要です。
採用担当者に負担が集中しないよう、外部サービスを利用するなど負担を軽減する体制構築が求められます。
採用方法の選び方【ケース別】
 採用方法は多様にありますが、すべての採用課題に対応できるような万能な手法はありません。
採用方法は多様にありますが、すべての採用課題に対応できるような万能な手法はありません。
そのため、採用を成功させるためには、求める人材や企業の抱える採用課題など、自社のニーズに合わせた適切な採用方法を選ぶことが重要です。
コスト、スピード、マッチ度、難易度の4つの側面において、どの採用方法を選択すると効果的かを表にまとめました。
| コスト | スピード | マッチ度 | 難易度 | |
| 求人広告 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 転職フェア | 〇 | 〇 | ||
| 人材紹介 | 〇 | 〇 | ||
| ハローワーク | 〇 | |||
| Webサイト | 〇 | |||
| リファラル採用 | 〇 | 〇 | ||
| SNS | 〇 | |||
| 就職課 | 〇 | |||
| インターンシップ | 〇 | |||
| ヘッドハンティング | 〇 | 〇 | ||
| アルムナイ採用 | 〇 | 〇 | ||
| ダイレクト リクルーティング |
〇 | 〇 | ||
| 人材派遣 | 〇 | 〇 |
コストとは採用活動にかかる費用のことを指します。
表では費用が安価、もしくは無料の採用手法に「〇」をつけています。
他の採用方法と比較して相対的に費用が低い手法を選択すると、採用コストが抑えられます。
スピードは人員を充足するまでの期間が早い手法を指します。
表では採用に至るまでのスピードが速い可能性が高い採用手法に「〇」をつけています。
欠員補充など採用の緊急度が高い際に重視しましょう。
マッチ度では、企業と応募者の双方において就職後に関する認識が一致し、採用につながりやすい手法に「〇」をつけています。
マッチ度が高いと採用後も定着しやすくなります。
難易度は専門職や人気の高い職種など、採用が難しい人材の確保に効果的な手法に「〇」をつけています。
採用難易度が高い場合に選択すると、採用につながりやすくなります。
ここからは、各課題のケース別に適した採用方法を詳しく見ていきましょう。
採用コストを抑えたい場合
採用コストを抑えて採用したい場合、有料の外部サービスを利用しない方法があります。
自社Webサイトや、リファラル採用、ソーシャルリクルーティングの他、ハローワークや検索エンジンなど無料で求人を掲載できる方法がおすすめです。
自社のホームページ内に採用ページを作成したり、公式のSNSで求人情報を拡散したりすることで、コストを抑えて採用活動がおこなえます。
求人サイトや人材紹介会社を通さない分、自社でリソースを確保する必要はありますが、中長期的な採用活動では効果が期待できます。
自社の人脈を活かしたリファラル採用では、紹介者である社員にインセンティブを支払うケースが多いですが、求人サイトを利用するよりも安価に採用活動をおこなえます。
地域を限定する場合には、不特定多数の人材にアプローチ可能なハローワークも有効です。SNSは、基本無料で利用できるものがほとんどのため、導入しやすい方法でもあります。
採用スピードを重視する場合
急な退職などによる欠員補充など、採用スピードを重視したい場合は、求人広告の掲載や人材派遣サービスを活用しましょう。
短期間で採用を成功させるためには、求人広告の打ち出しが非常に重要です。
自社の採用ターゲットを明確にし、採用ターゲットが転職する理由に思考を巡らせ、どのようなメリット・条件を原稿に打ち出せば応募につながるかを考えましょう。
人材派遣の場合は、希望する人材の採用要件をサービス会社に伝え、条件にマッチする候補者を紹介してもらいます。
あらかじめスキルを持っている人材を派遣してもらうことで、入社後の業務の引き継ぎもスムーズにおこなえるなど、即戦力としての活躍が期待できます。
アルムナイ採用も、過去に自社で働いていた人材に直接アプローチできることから、会社説明など細やかな説明が不要なため効率のよい採用が見込めます。
応募者とのミスマッチを防ぎたい場合
応募数は多いものの採用に至らない、入社後に早期離職する社員が多いなど、採用におけるミスマッチが課題の企業の場合、アルムナイ採用やリファラル採用、インターンシップなどの活用をおすすめします。
自社での勤務経験がある人材にアプローチするアルムナイ採用では、候補者が自社の企業風土や働き方、業務内容を知っているためミスマッチが起こりにくく、入社後の早期離職防止につながります。
リファラル採用では、自社を理解している社員に知人や友人を紹介してもらうため、候補者の人柄なども事前に知れるのが特徴です。
職務経歴書や短時間の面接だけでは見極めるのが難しい候補者の人柄について、自社の価値観や社風にマッチした人材かどうかの判断がしやすい採用方法と言えます。
インターンシップは、学生との接点が持てる貴重な機会であり、企業側と学生側の相互理解を深められるため採用後のミスマッチは少ないのが特徴です。採用難の現代において、導入する企業が増えています。
採用難易度の高い職種の場合
求人倍率が高い人気の職種や専門性の高い職種など、難易度の高い採用には、人材紹介やダイレクトリクルーティング、ヘッドハンティングなどが適しています。
転職顕在層にアプローチする求人広告サイトだけでは採用が難しく、転職潜在層にもアプローチする必要があるためです。
リファラル採用やソーシャルリクルーティング、ミートアップとの併用も効果的。企業が求める職種の採用に特化した求人広告サイトがある場合はそちらを利用するのも一つの方法です。
採用難易度が高い場合は、複数の方法を組み合わせておこなうことで効果の最大化を図りましょう。
人材採用を効率的に成功させるポイント
 効率的な採用活動を成功させるためには、注意すべきポイントがあります。
効率的な採用活動を成功させるためには、注意すべきポイントがあります。
主に3つのポイントについて以下でご紹介します。
求める人物像(ペルソナ)の明確化
採用活動を成功させるためには、まずターゲットとなる人物像(ペルソナ)を明確化させる必要があります。
関係各所にヒアリングし、求める人材の能力や人柄から「どのような人材がほしいのか」までをリストアップして採用要件を定義しましょう。
採用要件を明確にすることでミスマッチを防ぎ、内定辞退や早期離職の防止に役立つ他、面接官の評価にムラが生じるのを防いでくれます。
採用要件がきちんと定義できたら、ペルソナを設定します。
ペルソナとは、自社が採用したい具体的な人物像のことを指します。
その人物があたかも実在しているかのように、年齢や性別、家族構成、居住地、趣味嗜好、経歴、ライフスタイルなどを細かく設定して作り上げましょう。
現場が求める人物像と採用担当者が採りたい人材の認識のズレを減らしミスマッチを防ぐことで、結果として効率的な採用につながります。
複数の採用方法を併用する
複数の採用方法を組み合わせることで、採用効果の最大化を図ります。
必ずしも一つの方法にこだわる必要はなく、人材獲得が厳しい現代において、採用ターゲットに合わせた柔軟な採用活動が求められています。
例えば、ミートアップで接点を持った人材にカジュアル面談でアプローチするなど、複数の採用方法を組み合わせることでお互いに無理なくスムーズな採用活動がおこなえます。
パート・アルバイトを通年で募集している採用頻度が高い企業の場合、求人広告を掲載しつつ自社の採用サイトやハローワークなど無料でできる採用方法を併用することで、コストを抑えられます。
加えてSNSを活用した認知拡大を図るなど、恒常的な応募数の増加も期待できます。
採用方法にはそれぞれ向き不向きがあるため、複数の採用方法を組み合わせてカバーしながらバランスをとっていくことが理想的です。
分析・改善を繰り返す
効率的に人材活動をおこなうためには、採用活動の質の向上が不可欠であり、そのための第一歩が採用活動の分析および改善です。
現状課題の把握や戦略を見直すためのデータ分析方法には、主に以下の4つが挙げられます。
- 応募経路ごとの応募者数や採用率
- 求人媒体の費用対効果
- 選考過程別の歩留まり率
- 一人当りの採用単価
採用方法ごとに効果測定することで、自社の採用における課題の洗い出しができます。
採用活動の分析データは、どの採用方法のどのプロセスに問題があるのかを可視化でき、採用戦略の改善に役立てられます。
分析データを基に、採用フローの見直しをおこなって課題の改善を図ることで、採用活動の質と効率の向上が期待できるでしょう。
まとめ
 採用方法には、様々な種類がありそれぞれに特徴が異なります。
採用方法には、様々な種類がありそれぞれに特徴が異なります。
企業は自社の採用課題に応じた採用方法を選択し、採用担当者には企業の状況に合わせた最適な方法を見極める力が求められます。
従来の採用方法に加えて、ミートアップやSNSを活用したソーシャルリクルーティングなど、新たな方法も注目を集めています。
一つの方法に限定せず、ターゲットに合わせて複数の方法を組み合わせるなど効率的な採用活動をおこないましょう。
自社に最適な採用手法でお悩みの企業様は、ぜひカケハシ スカイソリューションズまでお問い合わせください。
貴社の求める人材の要件に合わせて最適な採用手法をご提案するだけではなく、選択された採用手法での成果を最大化するポイントまで合わせてお伝えいたします。
少しでもご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にご相談ください。
開催中の無料セミナー
貴社の採用要件、時代錯誤かも…!
ここを直せば応募が来る、求人票の見直しセミナー
開催日時:
2025年5月14日(水)11:00-11:30
まだ無駄なコストを払いますか?
キャリア採用のコストを見直し、賢く採用する方法
開催日時:
2025年4月24日(木)10:00-10:30
2025年5月20日(火)10:00-10:30
転職フェアへの出展を検討中の企業様限定
貴社は出るべき?出ないべき?
転職フェアで採用がうまくいく企業の共通点
開催日時:
2025年4月25日(金)10:00-10:30
2025年5月27日(火)10:00-10:30
おすすめのお役立ち資料
中途採用の他、各分野のお役立ちコラムを公開中
中途採用の知恵袋の他、新卒採用の知恵袋、社員研修の知恵袋、離職防止の知恵袋を運営しています。ぜひ合わせてご覧ください。
 |
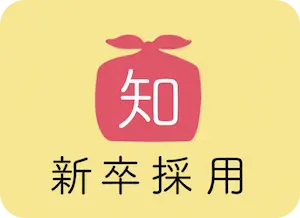 |
 |
 |

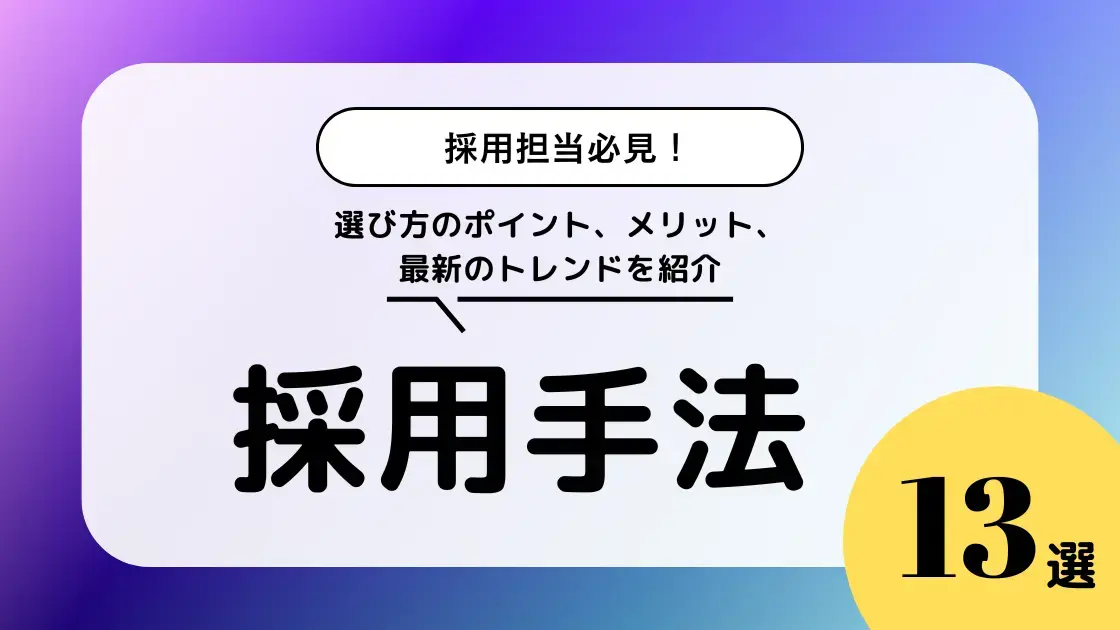
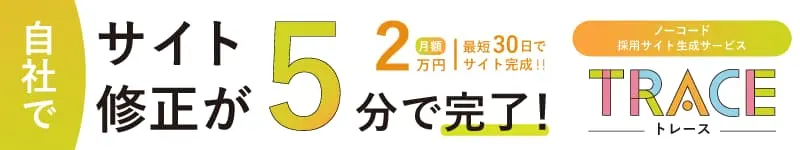


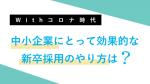
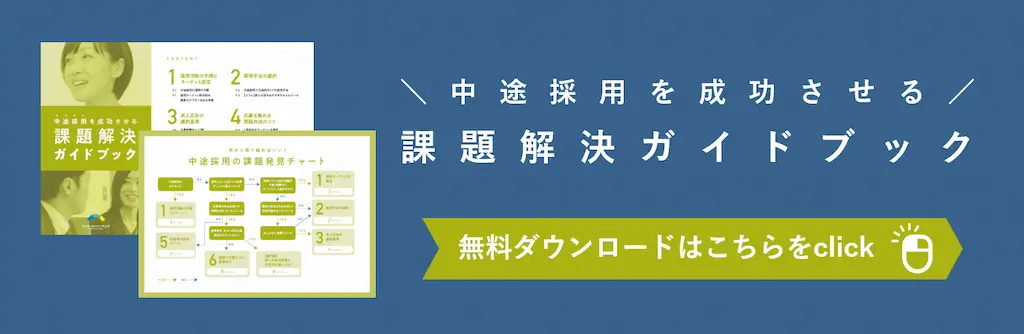
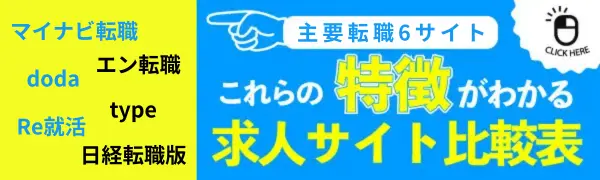
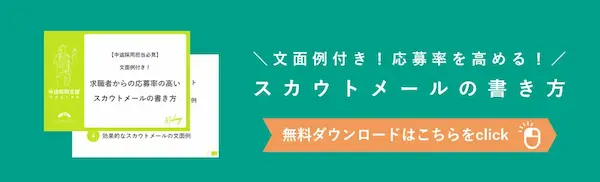
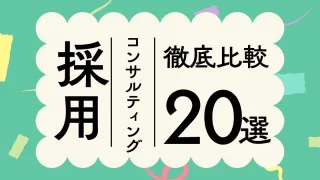
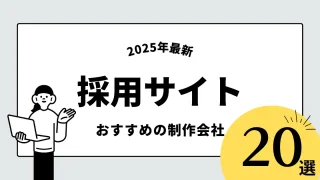
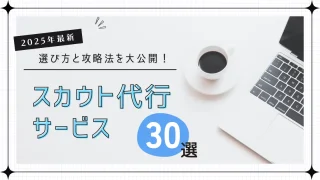
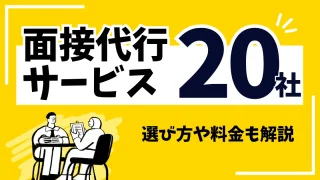
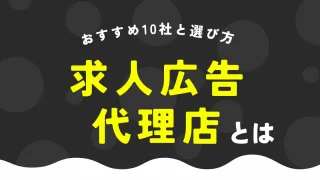
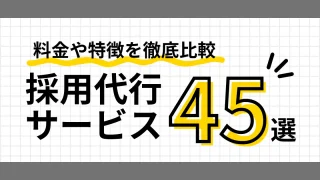
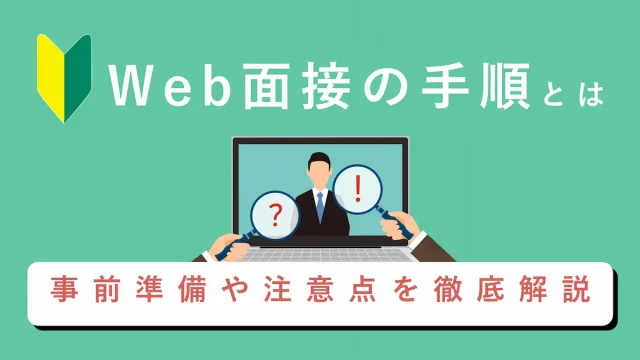
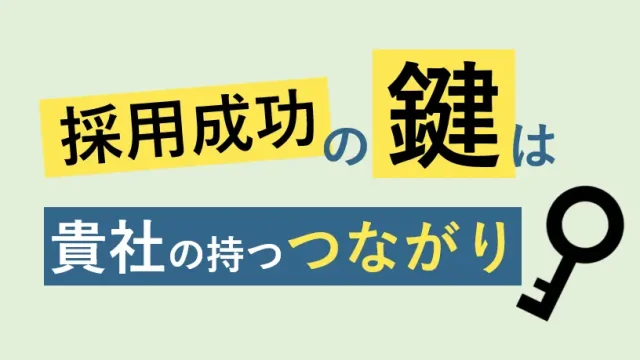
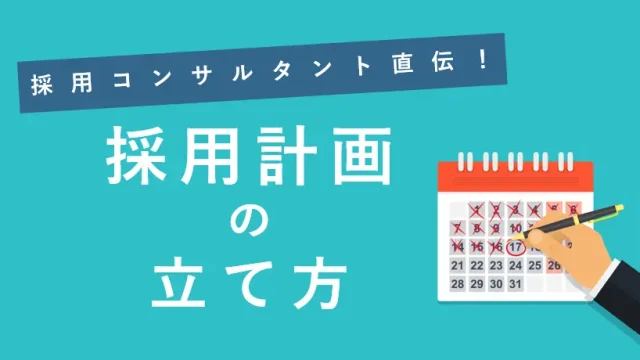
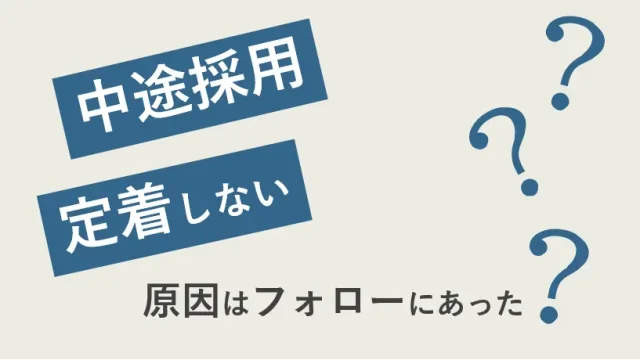
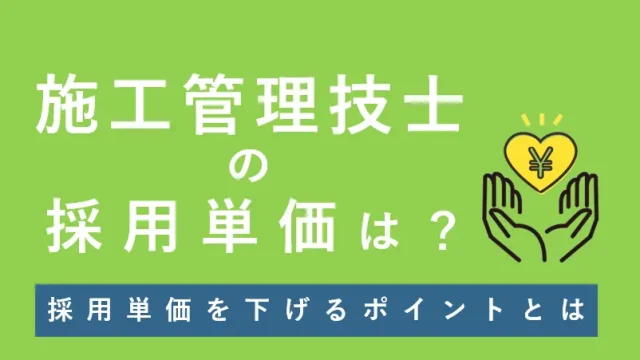
 ざんねんな求人票図鑑
ざんねんな求人票図鑑 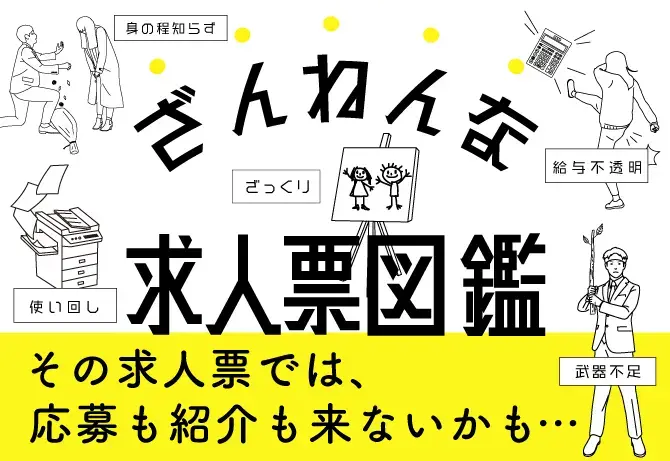
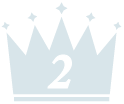 中途採用を成功させる課題解決ガイドブック
中途採用を成功させる課題解決ガイドブック 
 6つの主要転職サイトの特徴・違いが一目でわかる比較表
6つの主要転職サイトの特徴・違いが一目でわかる比較表